|
中山道ウォーク その7 平成14年5月21日(火) 宮ノ越から福島(寝覚)まで 平成14年5月22日(水) 福島(寝覚)から須原、野尻、三留野まで 先月4月19、20日は家内との初めての街道歩き。桜が満開の中、木曽路の上の4宿と言われる贄川から奈良井、薮原、宮ノ腰までのウォークを楽しんだ。あれから一月、季節は桜から新緑へと移った。今回の、中の3宿はあまり面白くなさそうとの事で家内はパス。元の独り歩きに戻って次の魅力の有る妻籠までをつないでおくことにする。 4月の中旬は雨ばかりで、今年の梅雨は早いのかと思われたが、その後は一転して爽やかなお天気続き。週間天気予報を睨みながら予定を立てる。今回の泊りは寝覚の元立場茶屋、「民宿たせや」さんに予約を入れた。さあどんな楽しみが待っている事やら。 初日 5月21日(火) 今回は原野の駅からのスタート。日は長いので早くに出発しようと思ったが木曽福島から原野までの1駅区間の普通列車が9時05分から11時28分まで無い。9時05分のは朝一番の新幹線を使っても間に合わない。仕方なく次のにし、豊橋8時54分の新幹線こだま441号、名古屋10時00分のワイドビューしなの11号と言ったのんびり時間で出発する。 しなの11号には修学旅行が居たため、指定が取れず自由席に回った人ですし詰め状態、幸い座って行けたが立っている人にはお気の毒。木曽福島乗換え11時28分、11時34分原野着。ここも無人駅、新緑のホームに降りたのは私一人。駅で小用を済ませ、体制を整えて11時40分出発。 今朝のニュースは中国領事館亡命問題解決に至らず。 宮ノ越から福島へ 「JR原野駅」 歩道橋の下が原野駅のホーム、無人駅である。ホームの向こうに八幡さんがあり、先月は桜が咲いていたが、今日は新緑が美しい。 
「庚申塔」 福島へ向けて歩き出してすぐ、左手に庚申塔など数体の石仏がある。 
「中央アルプスが見える」 左を見ると中央アルプスが綺麗に見える。先月より雪は少なくなった。 「明星巌公園から明星巌を見る」 右手に明星巌公園が有り、木曽川の向こうの山の中腹にある明星巌が良く見える。古い道中記にも巨岩として紹介されている。 「中山道中間点」 間も無く左手に中山道中間点の表示板がある。ここは江戸、京都双方から67里38町(約268㎞)で中山道の中間点。半分まで来たのだと言う感動を味わう。背後には中央アルプスが見え、如何にも木曽らしい風景である。  「石作駒石の墓」 旧道がスーパー和泉屋に突き当たる。その右の民家の庭にこの墓がある。石作駒石は漢学者で木曽代官山村家の家臣井沢喜兵衛の次男。伊勢で学び木曽に帰って師弟の教育にあたったと言う。 「草道となった中山道」 旧道はスーパーの脇から草道となり田の畦を行く。そのまま進んだら先に見える赤い屋根の家に入ってしまった。その家の方に道を教わって少し逆戻り、左へ進んで正沢川へ。ここでカッコウの声を聞く。久し振りに聞くカッコウの声に感激して暫く立ち止まる。 
「正沢川を渡る」 人が通るのがやっとと言う小さな鉄の橋で正沢川を渡る。 
「栗本の民家」 川の土手の坂を上がって進むと栗本の集落。出梁造りの家が数軒有る。 「庚申塔と薬師堂」 天神川の天神橋を渡ると左手に庚申塔、二十三夜塔等の碑と薬師堂がある。 「手習天神」 その先に赤い鳥居があって石段を上がると手習天神。木曽義仲を養育した中原兼遠が義仲の学問の神として京都の北野天神から勧進したものと言われ、境内のイチイの古木は銘木として知られている。 
「芭蕉句碑」 出尻の辺りで国道に出る。国道の左、山手のフェンスの切れ目にこの句碑がある。よほど気を付けていないと見逃してしまいそう。 おもひ出す木曽や四月の三九良狩 はせを 「関町信号」 蕎麦屋くるまやの先で国道から右に分かれ、開田高原や高山へ向かう国道361号線の木曽大橋の下をくぐり、再び国道と合流すると、間も無く関町の信号。国道はトンネルに入り、旧道は川沿いを関所へと向かう。山の中腹に『水とみどりと史跡のまち』とある。  中山道第三十七宿 福島宿 所在地 長野県木曽郡木曽福島町 最寄駅 JR中央本線木曽福島駅 本陣1、脇本陣1、旅籠14、 総人口972、家数158 上松へ 2里14町40間(9.4㎞) 「福島関所への関門」 道を跨いだ大きな関門が木曽福島の町への入口。左の坂を上がると関所跡。木曽川は右手の下を流れている。 
「福島の関所」 木曽川の斜面道路から高く聳える石垣の上に関所が復元されている。遠州新居関のように入り鉄砲と出女が取り締まられ、関守は尾張藩の木曽代官として木曽の森林を預かり大きな権力を持っていた山村甚兵衛が勤めていた。  「関所水」 昔から湧き続けている関所の水。 「復元された関所の建物」 昭和52年(1977)に復元された。上番所と下番所と呼ばれる二つの建物からなり、周りには柵がめぐらされ資料館として公開されている。 
「高瀬資料館」 関所の隣の門構えの家が高瀬家。山村家の臣で代々関所番を勤め、島崎藤村の姉園の嫁ぎ先、作品『家』のモデルとなったところ。 
「山村代官屋敷東門跡」 高瀬家から細い階段を下り道路に下りる。宿の道を右に折れ関所橋を渡って木曽川の北岸に出て左に曲がると玉石垣と水場。これが代官屋敷東門跡と代官清水。 「山村代官の下屋敷跡」 信号交差点、福島小学校の隣が屋敷跡。昔はこの小学校も含めた広大な敷地であった。今の建物は享保8年(1723)に建てられたもの。 
「藤村文学碑」 代官屋敷の道を隔てた向かいの、木曽教育会館の庭に藤村の文学碑があり、碑面に『夜明け前』序章の原稿が銅版で嵌め込まれている。 「芭蕉句碑」 隣の木曽郷土館の庭に小さな芭蕉句碑がある。 さ丶れ蟹あし這いのぼる清水哉 はせを 「本陣跡の福島町役場」 中央橋を渡って宿に戻り役場前交差点の左にあるのが木曽福島町役場で、福島の本陣の跡。それを示す標識の一つも無いのは寂しい気がする。 
「地酒七笑の店」 本陣跡の先左手に杉玉の酒林が下がった地酒七笑の店。 
「いわや旅館」 宿の右手真新しい旅館が昔の旅籠屋だった岩屋旅館。玄関先の常夜灯がそれと偲ばせてくれる。 「高札場」 宿の道は岩屋旅館の前で左に曲がる。左手に先程の七笑の蔵元があり突き当たり右に曲がると右手に高札場が再現されている。 
「観光文化会館」 さらに左に曲がると右手に観光文化会館がある。木曽踊資料室、無料休憩所の看板が架かり門の右手に水場がある。 「古い家並」 左に曲がると古い宿場らしい家並になる。  「井戸」 その先に井戸がある。深い井戸で江戸時代中期に掘られたもの。今でも清く冷たい水が湧いている。ここで右に曲がり中八沢橋を渡って再び右に曲がる。繁華街になり商店のそれぞれが昔の屋号を掲げているが、しかし普通の商店街である。 「JR木曽福島駅」 商店街を進み左にカーブして坂を上がると木曽福島駅前に着く。午後1時30分駅前の食堂で昼食をとり、駅のヒノキの厠で汗を拭い、小用を済ませて上松へと向かう。 福島から上松へ 「塩淵の一里塚跡碑」 駅前の御岳神社の裏から大同製鋼の脇を通る。ここはガイドに書いてあるから歩けるが、普通では誰も道とは思わない。坂を下り道に出てしばらく行くと、左手塩淵公民館の前に一里塚跡の碑。江戸より70里。 
「道祖神」 県道に出て木曽病院入口信号から再び左上に上がる細道で分かれる。登り切った右手に道祖神。 「中平立場茶屋跡」 その先左手に中平立場茶屋跡の解説板がある。 
「旧鉄道トンネルを行く」 旧道は草道となりトンネルの上を行くが途中で崩壊している。そのため危険を避け旧鉄道トンネルを行き、しばらく歩いて国道に合流する。 「御嶽山遥拝所」 元橋を過ぎ神戸で左に折れ、中央本線の線路をくぐり神戸の集落へ、ここを過ぎると鬱蒼とした杉林に入る。右手石段の上に石の鳥居、これが御嶽山遥拝所。でもここからはどんなにしても見る事が出来ない。何故ここに遥拝所を作ったのだろうか? 
「御嶽山」 しばらく進むと右手の視界が開け御嶽山を拝む事が出来る。右下には線路と国道が見える。 
「上松町に入る」 道が下りとなり線路をくぐって国道に出ると、まもなく上松町に入る。高い柱に『ようこそひの木の里、森林浴の町、 木曽上松町へ』 『森林浴発祥の地赤沢自然休養林、天下の名勝寝覚の床、中央アルプス木曽駒ケ岳、小野の滝、木曽の桟』とある。 「沓掛馬頭観音」 また板敷野で国道と分かれ左に入る。線路際を少し上がった所に沓掛の馬頭観音、祠と解説板がある 「沓掛の一里塚」 国道と合流する左の脇に沓掛の一里塚跡。江戸より71里、京より66里。解説板が立っているだけ。 
「木曽の桟」 山が谷に迫って右に緩いカーブをするところが木曽の桟。昔からの難所である。道路の下に昔の石積みが見える。 「対岸から見た木曽の桟」 対岸へ渡る橋から眺めたところ。近江八景になぞらえた木曽八景があり、桟もその一つで『桟の朝霧』と名付けられている。他には『与川の秋月』、『風越の晴嵐』、『御嶽の暮雪』、『小野の瀑布』、『寝覚の夜雨』、『徳音寺の晩鐘』、『駒ヶ岳の夕照』がある。  「芭蕉句碑」 木曽川の岸の大きな岩の上にある芭蕉句碑。 芭蕉翁 かけはしや命をからむ蔦かづら この碑は明和3年(1766)建立のものの最近の写しである。 「子規の歌碑」 対岸道路の山際にある正岡子規の歌碑。 「芭蕉句碑」 子規の歌碑に並んでもう一つ同じ芭蕉句碑がある。こちらは文政12年(1829)の建立。 「山頭火の句碑」 国道に戻って橋の信号交差点の左手にこの句碑がある かけはしふめば旅のこころのゆるるとも 山頭火 「木曽川沿いを歩く」 桟からは国道を行く。遥か遠くまで見通せる道をただひたすらに歩く。自分の辛抱強さに感心しながら。河原にはニセアカシアの花が白く咲いていて、時々キリの紫色の花も見える。  新茶屋を過ぎたところから歩道もガードレールも無くなる。大型トラックが情け容赦なく向かって来るし、道路の白線の外側は舗装の端で傾斜になっていて歩きにくく、全く生きた心地がしない。昔の旅人は木曽の桟で危険にさらされたが、今の旅人は貧困な道路行政のために危険にさらされている。国土交通省よ何とかしてくれ~。  中山道第三十八宿 上松宿 所在地 長野県木曽郡上松町 最寄駅 JR中央本線上松駅 本陣1、脇本陣1、旅籠35、総人口2,482、家数362 須原へ 3里9町(12.8㎞) 「上松宿の入口」 笹沢交差点で国道はバイパスとなって左のトンネルに分かれるが、旧道はそのまま直進。十王橋交差点で右に行くと赤沢森林公園、左山側へ入る道が上松宿への道。交差点の一画に標柱が立っており、『中山道上松宿入口上町』もう一面には『京へ六十五里四町、江戸へ七十里三十二町』とある。 
「お地蔵様や多数の石仏」 交差点の先に地蔵など数体の石仏がある。これは宿の入口十王堂の境内にあったもので、ここには高札場もあった。 「お地蔵様から十王橋と宿場を望む」 お地蔵様の後から十王橋とその先に続く宿場の家並が見える。 
「上町の古い家並」 宿に入って上町の約100mの間が度々に火災から逃れ、古い家並が昔の姿を伝えている。  「玉林院」 上町を抜け本町に入り左手に玉林院。木曽義元の次男玉林が創建し、山門鐘楼は明和3年(1766)の落成とか。 「白壁土蔵と黒壁の家」 宿に戻ると白壁土蔵に黒壁の家、落ち着いた宿場の雰囲気。 「脇本陣跡」 右手に脇本陣兼問屋であった原家。 
「本陣跡の歯科医院」 左手塚本歯科医院が本陣の跡。 
「上松宿の中心部」 本陣と脇本陣が向かい合ったこの辺り、かつては宿場の中心として活気に溢れていたであろう所だが、今は静まり返っている。 「本町一里塚跡」 宿場の道が右に曲がるその左手に本町の一里塚跡碑がある。京へ65里、江戸へ72里。  上松宿の桝形。一里塚の所で右に曲がり、直ぐ先の県道と合流する所で左に曲がる。 
「仲町から下町へ」 仲町から下町は宿の賑やかだった所だが、昔の様子を偲ばせる物は何も無い。 「駒ケ岳登山道」 標識に従い左折、右折し寺坂を上ると、左手に駒ケ岳への登山道、最近整備されたのか石段が積まれている。 「駒ケ岳大神宮碑など」 直ぐ先の十字路の角に多くの碑が立っている。駒ケ岳大神宮や駒嶽開山心明霊神など。 
「茂吉歌碑」 坂を上りきった所左手に上松小学校があり、その門前左手に斎藤茂吉の歌碑がある。 駒ヶ嶽見てそめけるを背後にし小さき汽車は峡に入りゆく 茂吉 「藤村文学碑」 門の右手に島崎藤村の文学碑がある。 山はしつかにして性をやしなひ、水は動いて情をやしなふ 洒落堂の記より 藤村 「尾張藩上松材木役所御陣屋跡」 左学校のグランドの土手の上に尾張藩上松材木役所御陣屋跡の石柱と解説板が立っている。この右側一帯が尾州陣屋と呼ばれ、木曽の山林の管理、保護、経営や取締りを行なっていた役所があった所。 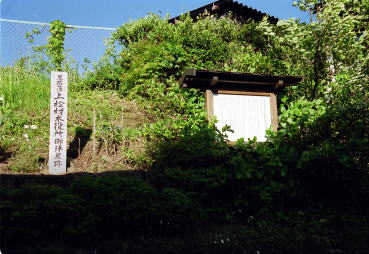
「諏訪神社」 続いて左に諏訪神社。石段を上がると学校のグランドでその奥に社がある。 上松から須原へ 「駒ケ岳」 左手に中央アルプス駒ヶ岳が見える。 「寝覚の立場」 中沢橋を渡り見帰の集落を過ぎるとまもなく寝覚の立場。右にたせやと越前屋が昔の姿のままで建っている。  「茶屋本陣のたせや」 たせやはこの立場の茶屋本陣で昔は蕎麦を食べさせていたが、今は民宿をしている。白い障子に赤い郵便ポストが良く似合う。今夜の泊りの予約が入れてあるが先に寝覚の床を見ておくことにする。 
「寿命蕎麦の越前屋」 こちらは寿命蕎麦の看板が掛かった越前屋。寿命蕎麦とは寝覚の床に戻ってきたと言う浦島太郎の長寿に因んで名付けられたもの。『続・膝栗毛』で野次・喜多が名物の蕎麦切りを食べたところ。旅館の看板が出ているが、今は泊めることはせず下の国道沿いに蕎麦の店を出している。 
「寝覚の床入口」 たせやと越前屋の間の道を下り、新しい越前屋の蕎麦の店の前の押しボタン信号で国道を渡ると正面に寝覚の床入口。 
「臨川寺」 その先が寝覚山臨川寺。竜宮から帰った浦島太郎が晩年をここで過ごし、彼が竜宮から持ち帰った弁才天の像や遺品を小祠に納め、寺を建てたのがこの寺の起源とか。寝覚の床への近道で、ここを通るだけで拝観料を取られる。 「臨川寺展望台からの寝覚の床」 展望台からは中央本線の鉄橋越しに木曽川を見下ろし、寝覚の床を見る事ができる。 「木曽七福神弁才天堂」 寺の境内にある弁天堂、木曽七福神霊場(楢川村大宝寺の寿老人から南木曾町光徳寺の恵比寿まで)の一つになっている。 「寝覚の床」 寺の庭から急な階段や坂道で崖を下り、中央本線鉄橋をくぐって木曽川の川原に降りる。以前に家内と来てここまで降りたことがあり、今回は二度目である。夕方5時を過ぎ人影もまばら、岩の上に夕日の景色を撮ろうとする人が三脚を立てていた。  「浦島堂」 浦島が寝覚めたところにお堂が建つ。 「子規の句碑」 臨川寺の境内には多くの句碑や歌碑などがある。これは正岡子規の句碑。 白雲や青葉若葉の三十里 子規 「芭蕉句碑」 昼顔に昼寝せふもの床の山 芭蕉 午後5時45分、たせやに戻って今夜の宿を乞う。ガラス戸をガラガラと開け敷居を跨ぐと中は土間、いわゆるタタキである。障子を開けて主人と女将さんが出てきて部屋に案内してくれる。部屋は二階の座敷で如何にも時代を感じさせてくれる。 早速風呂に入って今日一日の汗を流す。ここのお風呂はポリバスでシャワーも使えるので頭のてっぺんから足の先まで綺麗になり気持ち良くなった。食事に案内されたのが下の囲炉裏のある部屋。 今日の客は私一人だけ。手間を掛けさせるのが申し訳ないみたい。夕食のご馳走は地の物や山菜の料理。主なメニューは馬刺し、ごま豆腐、鱒の塩焼き、しし鍋、わらびの和え物、長芋のえごま和え、手打ちの蕎麦、蕗と筍の煮物、味噌汁に漬物など。 囲炉裏にかかった鉄瓶でお酒の燗をして頂く。最高の気分。満足、満足。 食事をしながら女将さんから色々な話を聞かせてもらう。ここは茶屋本陣で殿様や大名が下の臨川寺かここで 休憩される。そのどちらの時もここから寿命蕎麦を差し上げた。 古い文書が残っておりその様子が記されている。お代を貰うどころかこちらから布などを献上したなど面白い事が書かれている。その中の『御殿様御休扣帖・嘉永七年寅』と『御大名様方御休扣帖・天保九年卯』を見せてもらった。 今の家は明治2年に立て替えた家で、我々旅人にとっては心休まる建物も、毎日暮らす人には維持管理が大変とか。部屋にはストーブ、炬燵、夜具には毛布まで用意されていたがどれも使わずに寝る。夜間下の国道を走るトラックの音で度々目が覚める。 32,892歩 宮ノ越~上松 16.4㎞ ページ改良 平成22年11月4日 写真追加 平成22年12月4日 表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |