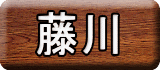
最寄駅 名鉄名古屋本線藤川駅
東海道第37宿
本陣1、 脇本陣1、 旅籠36、 問屋場1
総人口1,213、 家数302
岡崎へ 1里25丁
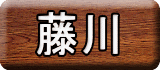 |
所在地 愛知県岡崎市 最寄駅 名鉄名古屋本線藤川駅 東海道第37宿 本陣1、 脇本陣1、 旅籠36、 問屋場1 総人口1,213、 家数302 岡崎へ 1里25丁 |
|
平成9年(1997)4月20日(日) 名鉄名古屋本線名電長沢駅より長沢の集落へ、本宿、藤川へと向かう。 |
 |
藤川宿東の棒鼻 山中八幡を過ぎ、約500メートルで国道は右へ大きくカーブし、名鉄名古屋本線を跨ぐが、東海道は国道と分かれほぼ直進する。 旧道のすぐ左手に東の棒鼻。これは平成5年(1993)に廣重の「藤川 棒鼻ノ図」を基に西の棒鼻と共に再現されたもの。見事にその雰囲気が出ている。 大きな木柱に「従是西藤川宿 東海道五十三次之内」と墨書されている。 |
 |
藤川宿の家並み 格子造りの古い民家が何軒か有って、宿場の名残を留めている。 こんな街道を歩く時は、心がワクワクして足どりが軽い。 |
 |
問屋場跡 道の脇にぽつんと問屋場跡の標石。宿が栄えていた頃は人足や馬で賑わったであろう所が、春の昼下がり、静まり返っている。 |
 |
本陣跡 宿の中ほど右手に森川家本陣の跡。 標石と藤川学区社会教育委員会の立てた解説板。 建物は残っていないが、裏手に回ると石垣が残っていて、当時の規模を知ることが出来る。 |
 |
脇本陣跡 本陣の隣に黒い門のある脇本陣跡。 この門は享保4年(1719)の大火の後に建てられたもの。 中は無人の藤川宿資料館、模型や古文書、各種資料が展示されている。 中でも、まぼろしの「むらさき麦」復元栽培の紹介が興味深い。 |
 |
西の棒鼻 右手藤川小学校の前に小公園のように整備された西の棒鼻。 「従是東藤川宿」の大きな木柱と常夜灯、そして歌川豊広の歌碑。 藤川の宿の棒鼻みわたせば杉のしるしとうで蛸のあし 歌川豊広 向かいの十王堂のそばに芭蕉の句碑。 爰(ここ)も三河むらさき麦のかきつばた 芭蕉 |
 |
一里塚跡 民家の花の植え込みに手作りの札が立てられている。 ほのぼのとした温かみが有って嬉しい。 |
 |
藤川の松並木 間も無く約400メートル続く藤川の松並木、この並木の真中を名鉄名古屋本線が横切る。 踏切の手前左手に吉良道道標。豊広の歌にあるうで蛸はこの道を通って藤川へ入ってきた。 |
 |
大平の一里塚 藤川の松並木を抜け国道と合流。約1キロ進んで再び左手に分かれると美合の町。ここにも松並木が残っている。 山綱川に架かる高橋の手前、左手に「天然記念物岡崎源氏蛍発生地」の標石と解説板。 乙川で旧道が途切れるため、国道の橋を渡りまた元の旧道へ。大平東の信号で国道を斜めに横切る。落着いた街を行くと左手に大平の一里塚。南の塚片側だけが残っている。今植わっている榎は、昭和28年の台風で倒れた先代に代わって植えられたもの。 国道に合流し、東名岡崎インター、岡崎環状線の信号を過ぎて間も無く右手へ分かれると欠町(かけまち)で、岡崎へ入る。 |
| 前回は名鉄の普通電車しか停まらない駅で区切ったため、往復に大変時間がかかり苦労をした。 そこで今回は急行停車駅の美合で区切る事にした。 藤川の宿は棒鼻が非常に印象的で、他の宿場には無い風情がある。 ここの松並木は御油に劣らぬ立派なものであった。 今日の歩数 20,329歩 |