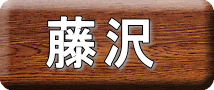
最寄駅 JR東海道線藤沢駅
東海道第6宿
本陣1、 脇本陣1、 旅籠45、 問屋場2
総人口4,089、 家数919
平塚へ 3里半
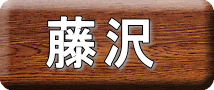 |
所在地 神奈川県藤沢市 最寄駅 JR東海道線藤沢駅 東海道第6宿 本陣1、 脇本陣1、 旅籠45、 問屋場2 総人口4,089、 家数919 平塚へ 3里半 |
 |
道場坂の一里塚 藤沢宿への長い下り坂の右手に標柱が一本。 緑の多いとても気持ちの良い下り坂、遊行寺坂とも呼ばれる。 この坂を下りきる手前には諏訪神社がある。 |
 |
遊行寺橋 坂を下った右手が遊行寺東門。 境川まで来て右に曲がると赤い橋、廣重の「藤沢・遊行寺」に描かれている。 この橋がお寺の正面になる。 橋の手前を左に行くのが鎌倉道。橋の向こうを左に行くのが江ノ島道。 |
 |
遊行寺冠木門 日本三大黒門の一つと言われる冠木門(かぶきもん)。 時宗総本山、正式には藤沢山無量光院清浄光寺。 鎌倉時代に「踊り念仏」で知られる一遍上人によって開かれた宗派で、その4代目の呑海上人によって正中2年(1325)に建立された。 本道の右手奥長生院に小栗判官・照手姫の墓がある。 |
 |
蒔田本陣跡 藤沢宿は蒔田源右衛門本陣が一つで、本町郵便局の向かいに標柱が立っている。 この宿には味のあるレトロな建物が何軒か残っているが、宿場そのものの名残を感じさせる物は無い。 街道から少し入った藤沢バイパス沿いに白旗神社があり、寒川比古命と源義経が祀られている。奥州で敗死した義経の首級がこの地に葬られたと言う伝説がある。 近くの藤沢本町を右に入った所に弁慶の首塚・源義経首洗井戸がある。 片瀬浜に捨てられた義経の首が、境川を遡り漂着したのを、里人が洗い清めたと言う。九郎尊神の小碑と九郎判官源義経公之首塚の碑がある。 |
 |
見附跡 小田急線の陸橋を渡って間もなく左手に見附跡の標柱。 ここが上方見附の跡で、ここまでが藤沢宿。 街道の向かいに錺屋(かざりや)さんがあり、2階の雨戸の戸袋に自慢の腕で打ち出した大きな風神雷神がはめ込まれている。見事なものである。 |
 |
大山道追分の道標 国道1号線が藤沢バイパスから分かれて東海道と合流する辺りに大山道の追分。 「是より右、大山みち」万治4年(1661)建立の道標と、そばには不動さんを乗せた大山道の碑が入ったお堂がある。 ここの右手鳥居をくぐって行く道が大山道。 |
 |
茅ヶ崎の松並木 大山道の追分を過ぎるとしばらく松並木が続く。 この辺りが辻堂で、一里塚が有った所だが見当たらず。 ただひたすらに西へ向かって歩く、 茅ヶ崎に入って再び松並木となる。古木ではないが街道らしい雰囲気になる。 |
 |
茅ヶ崎の一里塚 茅ヶ崎の駅入口の手前、元町交差点角に石垣に囲まれた塚が残されいる。 日本橋から14番目。 車の往来が激しく写真を撮るタイミングが難しい。 十間坂の右手に第六天神社。 |
 |
南湖の左富士之碑 千ノ川に架かる鳥井戸橋。この辺りを南湖と言い神奈川県内唯一の左富士の名所。 川の左手に夕日を背にした雄大な富士が見える。 橋を渡った左手畔に碑と説明板がある。廣重も「南湖の松原左富士」の作品を残している。 京へ上る東海道で富士が左に見えるのは、ここと吉原だけ。 橋を渡った右手に鶴峰神社の赤い大鳥居、脇に弁慶塚の標石。 |
 |
馬入橋 今宿、番屋等の地名に興味をひかれながら歩くるうちに、相模川に架かる馬入橋に至る。 この川は馬入川とも呼ばれ、昔は舟渡しであった。正面に富士が見える。 |
| 相模川を渡ると平塚市街、次の平塚宿はJR平塚駅の先。 今日の行程は駅までとし、泊まりの小田原のホテルへと向かう。 お天気に恵まれ、富士も良く見えて、単調な歩きのなかで目を楽しませてくれた。 しかし肉眼ではあんなに綺麗に見えた富士が私のカメラには全く写っていない。 誠に残念。 今日の歩数 43,018歩 |