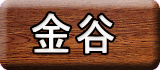
最寄駅 JR東海道線金谷駅
東海道第24宿
本陣3、 脇本陣1、 旅籠51、 問屋場1
総人口4,271、 家数1,004
日坂へ 1里24丁
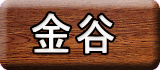 |
所在地 静岡県榛原郡金谷町 最寄駅 JR東海道線金谷駅 東海道第24宿 本陣3、 脇本陣1、 旅籠51、 問屋場1 総人口4,271、 家数1,004 日坂へ 1里24丁 |
| 平成9年7月21日(月)休日、海の記念日の代休 梅雨明け後の晴天、今年は梅雨前線が南の海上に下がって消滅したため、涼しくて、爽やか。 金谷駅前を10時10分出発す。 |
 |
東橋 大井川橋を渡ってすぐ南へ、堤防を下りて旧道に戻る。 新堀川に架かる東橋、ここに金谷宿の道標。 橋を渡って左に200メートルで宅円庵、日本左衛門の墓がある。(芝居では日本駄右衛門)白波五人男の頭目で南郷力丸と共に実在した人物。 大井川鉄道の踏切を越え、大代橋、清水橋を渡ると金谷宿に入る。 大井川鉄道のSLの汽笛が遠くから聞こえ、何とも懐かしい気分になる。 |
 |
佐塚屋本陣跡 上り坂の街道を行くと、右手に佐塚屋本陣跡。 その先すぐ右手に柏屋本陣跡の標識。 |
 |
一里塚跡 金谷駅手前ガードの脇に一里塚跡の看板。江戸へ五十三里とある。 頭の上に大井川鉄道の電車が停まっている。 ここをくぐって右折、駅の裏手を通って金谷坂の石畳へと向かう。 左手上に長光寺、境内に芭蕉句碑。 道のべの 木槿は馬に 喰われけり はせを |
 |
旧東海道石畳入口 県道を横切る手前に秋葉山の祠と碑がある。 この碑は陽物(ペニス)にそっくり。 県道を横断した所に大きな旧東海道石畳入口の看板と石畳茶屋の看板がある。 |
 |
金谷坂の石畳 ここから一気に牧の原台地へと上る。 わずか30メートルばかり残っていた石畳を、平成3年に町民挙げての「平成の道普請」で430メートルに復元された。 上り口右手に石畳茶屋。資料展示室、食堂、売店があり菜飯田楽を食べさせる。 |
 |
芭蕉句碑 金谷坂を上りきった所に明治天皇御駐輦阯碑とこの句碑がある。 馬に寝て 残夢月遠し 茶の烟 芭蕉 坂の上は牧の原台地、茶畑が広がる。 |
 |
宗行卿詩碑・日野俊基卿歌碑 一部石畳の復元された菊川坂を下ると、国道一号線の高架下にひっそりとした間の宿菊川の集落がある。 間の宿村おこし施設の前に二つの碑。 東海道名所図会の菊川宿に書かれた中御門前中納言宗行卿の歌碑と、その話に涙して詠んだ後醍醐天皇の近臣日野俊基卿の歌碑。 |
 |
小夜の中山夜泣き石 国道1号線中山トンネルのすぐ上にある。元は旧道に有ったものが明治初年、東京の勧業博覧会に出品後、元の位置に戻らずここに置かれている。 山賊に殺された妊婦の泣き声が石から聞こえたが、弘法大師の読経で霊が鎮まったと言う。国道沿いに子育て飴の小泉屋がある。 青木坂から西の西坂までおよそ3キロが、なだらかな丘陵地帯の小夜の中山。 |
 |
久延寺の夜泣き石 久延寺は山内一豊が関が原へ向かう家康を接待したところ。本尊は子育て観音。 境内に家康手植えの松、芭蕉句碑、そしてここにも夜泣き石がある。 |
 |
茶店扇屋 久延寺のとなりにある茶店。名物おばあちゃんが子育て飴を売っていた。 向かいが小夜の中山公園。中に西行歌碑。 この先に一里塚跡、紀友則歌碑、白山神社、妊婦の墓、芭蕉句碑、夜泣き石跡、廣重絵碑小夜の中山峠と見るべき物がいっぱい。 |