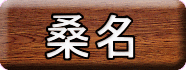
最寄駅 JR関西本線桑名駅
東海道第42宿
本陣2、 脇本陣4、 旅籠120、 問屋場1
総人口8,848、 家数2,544
四日市へ 3里8丁
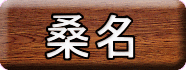 |
所在地 三重県桑名市 最寄駅 JR関西本線桑名駅 東海道第42宿 本陣2、 脇本陣4、 旅籠120、 問屋場1 総人口8,848、 家数2,544 四日市へ 3里8丁 |
| 平成10年(1998)1月17日(土) 阪神淡路大震災から3年目。街道に興味を持って歩き始めたが、全行程がどんなものか想像が出来ず、 何処まで続けられるかの見通しも無く自信も無かった。でも一回一回の積み重ねで半分以上を歩いた事となった。 自宅からは次第に遠くなり足場が悪くなってきた。これからは行ける時に行ける所を歩くので宿の順番と歩いた時とがバラバラになる。 青空キップで東海道線、関西線と乗り継いで桑名へ。七里の渡しを渡った積もりにして、桑名からスタートする。 |
 |
七里の渡し 熱田の宮から桑名まで、海路七里を無事に渡ってたどり着くのがここ桑名の渡し。 前には揖斐川が流れ広大な景色。 伊勢湾台風の後、高い防潮堤が作られたため道路と遮られ、渡し場の機能は失われている。 |
 |
伊勢一の鳥居と常夜灯 七里の渡し場に伊勢一の鳥居と常夜灯がある。 伊勢の国の東の入口と言うことで一の鳥居が立てられている。 常夜灯は戦後鍛冶町から移されたとか。 |
 |
桑名宿の中心部 七里の渡しを上がってすぐ右手にある。 大塚本陣は船津屋、駿河屋脇本陣は旅館山月。 その間に本陣跡・脇本陣跡の説明板、船津屋には久保田万太郎句碑、山月には唄碑がある。 唄碑には「勢州桑名に過ぎたるものは銅の鳥居と二朱の女郎」 |
 |
本陣跡船津屋 元は大塚本陣、泉鏡花の「歌行灯」の舞台となった料亭。 黒塀にはめ込まれるような形で久保田万太郎の句碑がある。 かわをそに 火をぬすまれて あけやすき 小説の中に「時々崖裏の石垣からかわうそが入り込んで板廊下や厠に点いた燈を消して、悪戯をするげに言ひます」とあるのによる句。 |
 |
銅の鳥居 東海道は渡しを上がって正面の道。歩き易いように道路が整備され案内標示も行き届いている。 右手に桑名神社(春日神社とも言う)、唄に謡われた青銅の大鳥居と「日本一喧しい祭り」と称される石取り祭りで有名。 |
 |
天武天皇社 左に桑名城址を見て京町で右折、石取り会館を右に京町交差点を渡り、毘沙門堂で左折。京町見附、吉津屋見附、七曲見附と複雑なコースをとって西へと向かう。 右手に天武天皇社。壬申の乱のときに桑名に留まったことに由来する神社。 |
 |
矢田の立場 国道1号線を渡り、谷田町で突き当たる。この辺りが立場跡。 交差点の角に火の見櫓が復元され半鐘が下がっている。 ここで左折、南へと向かう。 |
 |
町屋橋跡 日立金属の工場を右に見て国道258号線を過ぎると員弁川(町屋川)に出る。 昔はここに橋が架かっていた。今はすぐ左を通る国道1号線の橋を渡る。 |
 |
町屋川の常夜灯 町屋川の土手に文政元年(1818)建立の常夜灯と、脇に明治初期の道標が立っている。 国道1号線の橋を渡ったら再び右手の東海道に戻る。古い家並みが続く。 近鉄名古屋線伊勢朝日駅の手前で踏切を渡る。この辺りが小向立場跡で焼き蛤を売っていたとか。 朝明川手前の土手に多賀大社の常夜灯。この朝明橋を渡ると四日市市。 |
 |
冨田の一里塚跡 関西本線を渡り三岐鉄道のガードをくぐると西富田町。ここで左折し今度は三岐鉄道と近鉄名古屋線のガードをくぐる。 ガードをくぐってすぐ右手に大きな石碑で一里塚跡。冨田の立場が有った所。 冨田を過ぎると右手に山神のみやと言われる茂福神社。 米洗川には常夜灯。 羽津町には1本の松が残っており、ここが街道が街道であることを示している。 |