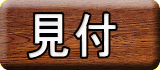
最寄駅 東海道線磐田駅
東海道第28宿
本陣2、 脇本陣1、 旅籠56、 問屋場1
総人口3,953、 家数1,029
浜松へ 4里7丁
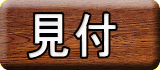 |
所在地 静岡県磐田市 最寄駅 東海道線磐田駅 東海道第28宿 本陣2、 脇本陣1、 旅籠56、 問屋場1 総人口3,953、 家数1,029 浜松へ 4里7丁 |
 |
阿多古山一里塚 遠州鈴ヶ森から下ってくると、愛宕神社と一里塚跡がある。 階段を上った丘の上、神社本殿の後ろに大きな一里塚の石柱があり、ここから西を望むと足下に見付の宿が一望で来る。 |
 |
矢奈比売神社と悉平太郎の像 塚から100メートル程右に行くと矢奈比売(やなひめ)神社、別名見付天神とも呼ばれる 旧暦8月10日、闇の中で踊る裸祭で有名。 ここには信州駒ヶ根と関係した伝説がある。正和年中(1312頃)ここに怪物が住みつき、毎年人身御供を要求した。それを聞いた一実坊という旅僧が、信濃の光前寺にいた悉平太郎(しっぺいたろう)という犬を使って怪物を退治した。光前寺にはこの犬の墓が有り、一実坊が謝恩の為に奉納した大般若経600巻が残っている。 |
 |
脇本陣跡 塚からすぐ木戸跡で見付の宿に入る。賑やかな街並みになり綺麗に整備されている。 西への道を「宿場通り」と呼び、脇本陣跡の木製の標示が立てられている。 高札場跡、大見寺の前に見付宿の石碑、問屋場跡、脇本陣跡と街道の両側に並ぶ。 |
 |
高札場跡 宿の中程右手に高札場跡の立札。 そこから奥に入ると旧見付小学校と式内社淡海国玉神社がある。 旧見付小学校は明治8年(1875)の建造、現存する日本最古の洋風木造小学校校舎で、明治16年に4階建てから5階建ての今の姿になった。現在は資料館として昔の学用品や人形などが展示されている。 |
 |
本陣跡 宿の両側に本陣跡の標示。 標示のみで、その面影は無い。 |
 |
遠江国分寺跡 西坂町で左折、南へ曲がると西の木戸。道は「天平通り」となる。直進すると池田道本坂越えの姫街道。 国道1号線を横切り更に進むと右手磐田高校の北側に国府跡、南側に国分寺跡で今も礎石が残っている。 |
 |
府八幡 国分寺の向かい街道の左手にある。奈良時代に遠江の国造桜井王が国府の守護神として石清水八幡宮を勧請したもの。 境内の一角に万葉歌碑。聖武天皇と桜井王の問答歌が刻まれている。 遠江守桜井王、天皇に奉る歌一首 九月のその初雁の使いにも 思う心は聞こえ来ぬかも 一六一四 天皇の賜へる報和の御歌一首 大の浦のその長浜に寄する波 寛けく君を思うこのころ 一六一五 天平の頃この辺り一帯は遠州の中心部であった。 |
 |
宮之一色一里塚跡 「天平通り」を南下した街道は磐田駅前東町で右折し、天竜川に向かって西へと進む。 「天平通り」は駅前の商店街になると、「ジュビロード」になる。さすがサッカーの街。 西へ向かっておよそ2キロ右手に一里塚跡。その先森下には松が残っている。 長森の立場を過ぎると間も無く天竜川に至る。 |
 |
天竜川 昔は船で渡ったが、今はトラスブリッジの古い橋と、その上流にコンクリートの新しい橋とがある。 どちらにも歩道が無く路側を歩くのだが、横を大型トラックが走り抜けると、全く生きた心地がせず、昔の舟渡しの方がよほど危険が少なかったのではないかと思った。 |
| 今回は掛川から袋井、見付まで歩いた。見るべきところが多く大変楽しいコース。 中でも見付は狭い地域に色々なものが凝縮されていて魅力のある宿場である。 1800年頃の創業と言われる料理屋「大孫」の宿場弁当を頂けたのが見付の印象をより良い物にした。 今日の歩数 39,261歩 |