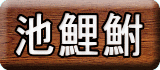
最寄駅 名鉄名古屋本線知立駅
東海道第39宿
本陣1、 脇本陣1、 旅籠35、 問屋場1
総人口1,620、 家数292
鳴海へ 2里半12丁
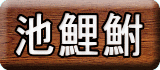 |
所在地 愛知県知立市 最寄駅 名鉄名古屋本線知立駅 東海道第39宿 本陣1、 脇本陣1、 旅籠35、 問屋場1 総人口1,620、 家数292 鳴海へ 2里半12丁 |
| 平成9年(1997)5月11日(日) 母の日、ご近所の奥様の小品盆栽展を家内と見に行く予定だったが、それをキャンセルして歩きに出る。 皆さんごめんなさい。 名鉄新安城駅下車、今本町から西へと向かう。 |
 |
八橋山無量寿寺道標 猿渡川を渡ると知立市に入る。初めての信号の角に古い石の道標。 「従是四町半北八橋、業平作観音」元禄9年(1696)建立 伊勢物語で、在原業平がカキツバタを見て、その5文字を語句の上に据えて詠んだ歌で有名なところ。 丁度今はカキツバタの頃、「八橋かきつばた祭り」の幟が立っていた。 |
 |
来迎寺の一里塚 道標のわずか先、左手に大きなマウンドの一里塚。 南側の塚だけが残っていて、クロマツが植えられている。 |
 |
万葉歌碑 やがて知立の松並木になる。そのかかりの左手明治用水解説板、この部分は暗渠にしてカキツバタの植わった公園になっている。 左手に「旧東海道第三十九番目の宿池鯉鮒」の石柱。 左手に小林一茶の句碑 はつ雪やちりふの市の銭叺(ぜにかます) 一茶 左手に万葉歌碑 大寶二壬寅年十月 持統上皇幸三河国時歌 長忌寸奥麿 引馬野爾 仁保布榛原 入乱 衣爾保波勢 多鼻能 知師爾 |
 |
馬市之址碑 万葉歌碑に並んで馬市之址の碑。 この辺り廣重の描いた馬市が立った所。 碑の裏側に麦人の句 杜若名に八つ橋のなつかしく 蝶つばめ馬市たてしあととめて |
 |
池鯉鮒宿問屋場之跡 国道を斜めに横断し南側の市街地へ入る。 銀座商店街が宿の中心、右手マンション手前角に問屋場跡碑。 左手が本陣跡のはず、探したが手懸かりを見つける事が出来なかった。 T字路を右折、突当たりを左折、国道155号線を地下道でくぐると知立神社。 |
 |
知立神社 延喜式内社、日本武尊が東国平定のおり、この地で国運の発展を祈願し、数々の危難を脱して平定に成功、よって皇大神を祀った。 昔から蝮よけ、長虫よけのお札で有名。5月の祭礼には壮麗な山車が出て、からくりや山車文楽で賑わう。 境内に芭蕉句碑 不断立つ 池鯉鮒の宿の 木綿市 芭蕉 |
 |
逢妻川 神社を出ると逢妻川に架かる逢妻橋、昔は宿の出口で池鯉鮒大橋と呼ばれた。 橋を渡るとすぐに国道と合流する。 国道に出て次の信号が一里山。塚は失われても地名だけが残っている。 |
 |
今川の家並 今岡町で国道から左に分かれると、落着いた街道らしい雰囲気の今川の集落。 この辺り「いも川のうどん」と言う平たく打った紐状のうどんが名物であった。 |
 |
境橋 今度は今川町の信号で国道を北へと渡り、境川に架かる境橋を渡る。 この川が三河と尾張とを分けており、今は刈谷市と豊明市の境である。 橋を渡ると旧道は国道と再び合流する。 その地点で国道は1号線と23号線とに分かれ、23号は左へ大きくカーブしながら名鉄を跨いでゆく。 |
 |
阿野の一里塚 車の流れが少なくなった国道を直進すると、間も無く道の両側に一里塚。 「国指定史跡阿野一里塚」の白い標柱と、向かい側には「史跡阿野一里塚」の石柱と解説板。 当時は一里ごとに街道の両側に築かれたが、今も両側に残っているのは非常に珍しく、昭和11年12月に国の史跡に指定された。 街道を進むと左手に名鉄が近付いてくる中京競馬場前駅の手前でガードをくぐる。 すぐ左が桶狭間の古戦場。 やがて国道から名鉄に沿って右に分かれると間の宿、絞りで有名な有松に入る。 |