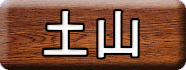
最寄駅 JR草津線三雲駅よりバス「田村神社前」
東海道第49宿
本陣2、 脇本陣0、 旅籠44、 問屋場1
総人口1,505、 家数351
水口へ 2里半7町
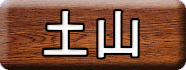 |
所在地 滋賀県甲賀郡土山町 最寄駅 JR草津線三雲駅よりバス「田村神社前」 東海道第49宿 本陣2、 脇本陣0、 旅籠44、 問屋場1 総人口1,505、 家数351 水口へ 2里半7町 |
 |
田村神社 峠を少し下ると国道に出る。そこは滋賀県土山町。振り返ると国道の先はトンネルでその上に万人講石灯籠だ聳えている。 峠を越えて近江側に入ると、なだらかな下りとなり、国道を歩く。第2名神の高い橋をくぐり、山中の一里塚を過ぎ、蟹ヶ坂を過ぎると田村神社。 祭神は鈴鹿の鬼を退治した坂上田村麻呂、厄除けの神様として信仰を集めている。 |
 |
かにが坂飴 神社の向かいに、土山名物・厄除け蟹ヶ坂飴の店。 昔このあたりに大きな蟹のお化けが出て旅人を悩ませていた。人々が困っていると都の僧が蟹に向かって説法した。蟹は随喜の涙を流し、甲羅が8つに割れて消え失せた。僧がこのときの蟹の血で作ったのが蟹ヶ坂飴で、今も売られている。 街道はこの店の横を通り、すぐに右折し、土山宿に向かう。 |
 |
東海道土山宿碑 飴屋からしばらく進むと、右手に土山宿の碑。 連子格子の町屋風の家が目立つようになり、それぞれの家に、昔の地名と商いの種類、屋号を書いた木札が掲げられている。 |
 |
東海道一里塚碑 幾野の一里塚、街道の右手、民家の玄関先にある。 街全体がこの宿場を守ってゆこうとしている事が感じられる。 |
 |
森白仙終焉の地・井筒屋跡 一里塚から地蔵堂を2つ過ぎた街道の右手。 森白仙は文豪森鴎外の祖父。石見国津和野藩亀井家の典医で参勤交代に従い江戸より帰途、文久元年(1861)10月7日ここで病死。近くの常明寺に葬られた。 |
 |
二階屋脇本陣跡 街道の右手。 土山の宿は、本陣から旅籠、商家にいたるまで、その跡を石碑や看板で標示されており、街道を歩く我々は当時の街の中を歩いている様な気分にさせられる。 |
 |
典型的な土山宿の民家 この様な家が数多く残されており、落着いた宿場である。 |
 |
土山宿本陣跡 街道の右手。寛永11年(1634)3代将軍家光の上洛に際して設けられ、明治3年(1870)まで続いた。明治天皇が即位後初の天長節を土山で迎えられた事で知られ、建物の隣に明治天皇聖跡の大きな碑が立っている。 2階は漆喰塗り籠の白壁、1階は半分が1メートル程奥に引き込んだ格子造りの大きな屋敷。 |
 |
大黒屋本陣跡 街道の右手。土山宿問屋場跡と高札場跡の3つの碑が並んでいる。 向かいには土山宿陣屋跡がある。代官その他の役人が在住したところ。 左に入ると森家の墓がある常明寺。 |
 |
国道1号との合流地点 東海道土山宿の碑と常夜灯、解説板が立てられている。 この辺りまでが土山宿。 |
| 鈴鹿の峠は守り易く攻め難いと言われるが、自分の足で歩いてみてそれが実感としてわかった。 坂下からの八町二十七曲りの急坂は箱根と比べられる程であるが、上りきってしまうと下りは緩いダラダラ坂、 今までの上りが何だったのかと拍子抜けするくらいである。 今日の行程は土山宿を出たところまでとし、予約しておいた水口のホテルに泊まる。 今日の歩数 26,875歩 |