|
中山道ウォーク その4
平成13年9月28日(金) 沓掛から追分、小田井、岩村田、塩名田、八幡、望月まで
平成13年9月29日(土) 望月から芦田、長久保、和田まで
前回の8月には碓氷峠を越えて、信州浅間三宿の沓掛まで来た。今回は信濃路を歩く。この間に世界を揺るがす大きな事件が発生した。9月11日のアメリカでの同時多発テロである。ニューヨークの世界貿易センタービルとワシントンの国防総省ペンタゴンに乗っ取られた旅客機が突っ込むなどして、数多くの犠牲者が出て、未だに犠牲者の数が6,000人位かと言われ、確かな数も把握出来ない状態である。日本では国際貢献を理由に自衛隊の出動が約束され、国会で論戦となっている。
初日 9月28日(金)
今回も行きは夜行バス伊良湖ライナーを利用する。先回のような電車の遅れは無く順調にスタートする。しかし、東京着がダイヤでは5時50分なのに5時に着いて、下ろされてしまった。「早過ぎるー、もっと寝かせてくれー」と文句を言いたい。キップの発売窓口が開くのを30分も待って、朝食を取って、そして始発6時26分の長野新幹線に乗車する。高崎辺りから雨、軽井沢は寒い。半袖のポロシャツ姿は私だけ。7時39分のしなの鉄道で中軽井沢へ。装備を整え7時45分スタートする。
今朝のニュースは、米支援新法政府与党詰めの協議。近鉄12年ぶり優勝、北川の代打逆転満塁サヨナラホー
ムランでのリーグ優勝決定は史上初。
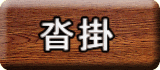
中山道第十九宿 沓掛宿
所在地 長野県北佐久郡軽井沢町長倉
最寄駅 しなの鉄道中軽井沢駅
本陣1、脇本陣3、旅籠17、総人口502、家数166
追分へ 1里3町(4.3㎞)
「脇本陣跡の旅館」
宿の中央中軽井沢の信号を左折、駅前を再び左折した先に旅館桝屋本店の看板。その看板に旧脇本陣とある。雨がほんの少し降っているが、傘を差す程ではない。

「脇御本陣蔦屋跡碑」
信号に戻り街道のすぐ先、左、銀行の駐車場奥に未だ新しい石碑が立つ。ここが脇本陣蔦屋の跡。
「旧本陣土屋氏宅」
その先右手に石塀に囲まれたモダンな住宅がある。表札に本陣土屋と刻まれている。ここが皇女和宮も泊まった沓掛宿の本陣跡。昔を偲ばせるものは無いが表札に本陣と入れてあるところが嬉しい。

「沓掛宿西木戸跡」
街道は上田信用金庫の前で国道から左に分かれる。この辺りが宿の西の木戸跡。木戸跡の手前を右に入る道が草津街道。その角に「右くさつ」の古い道標が立つ。
沓掛から追分へ
「女街道入口」
古宿を過ぎ国道に合流してバイパスをくぐる。再び左へ分かれ借宿集落へ、そこの変形四差路を左に入るのが女街道。女の通行に厳しかった横川の関を避けるルートで、右角に解説板が立っている。この向かいが借宿立場茶屋跡。国道に有った気温の表示板に只今の温度10℃と出ている。吐く息が白い。寒い。
「遠近神社」
借宿のほぼ中央右に赤い鳥居の遠近神社。
「杉玉の酒林が架かる民家」
借宿には古い建物が幾つか残っている。右手にある杉玉の酒林が架かった家も絵になりそう。庭のドウダンツツジの葉がもう真っ赤に紅葉している。この辺りから傘を差す。

「馬頭観音碑」
借宿の右手に大きな馬頭観世音碑。高さ約4m。馬への期待と感謝の気持ちが込められている。
「追分の一里塚」
国道に合流し、追分宿に入る手前に追分の一里塚。江戸より36番目。道の両側に塚が残り、それぞれに解説板が立てられている。これは右手のもの。
「追分の一里塚」
こちらは左手のもの。
「追分宿の入口」
国道から右に分かれて追分の宿へと向かう。前を行く人も同じ街道歩きの人。
「浅間神社」
坂を下る途中の右手に「あさま神社」。隣に追分宿郷土館がある。
「油屋寄贈の常夜灯」
神社境内に脇本陣油屋が奉納した不動尊や常夜灯がある。
「芭蕉句碑」
同じく境内に有名な芭蕉の句碑がある。寛政5年(1793)の建立。
ふき飛ばす石も浅間の野分哉 芭蕉翁
その他追分節発祥の地碑等もある。

中山道第二十宿 追分宿
所在地 長野県北佐久郡軽井沢町追分
最寄駅 しなの鉄道信濃追分駅
本陣1、脇本陣2、旅籠35、総人口712、家数103
小田井へ 1里10町(5.0㎞)
「堀辰雄文学記念館」
うとう坂を下って昇進橋を渡ると追分の宿に入る。宿内の神田坂を下った左手に記念館の看板。建物は木立の奥にある。
「油屋」
右手に旅館油屋。元は左手に有った脇本陣、多くの文学者が滞在したことで有名。
「古い建物の骨董店」
油屋の隣、右手の骨董屋さんは街道らしい雰囲気を出している。
「本陣跡」
右手に明治天皇行在所跡の石碑の立っている所が旧本陣の土屋家。門柱に埋め込まれた白い表札には中山道追分宿旧本陣とある。

「高札場」
右手に復元された追分宿高札場。
「浅間山道路第一詣石」
本陣跡の左端に石柱。ここから右に入る道の標識で、先の追分からの草津道と峰の茶屋で出会う。
「蔦屋の下げ看板」
街道の右手、蔦屋の古い看板が軒から下がっている。

「泉洞寺」
街道の右手、ここの奥、墓地入口に堀辰雄が愛したと言う半迦思惟石仏がある。
「半迦思惟石仏」
高さ40cm程の可愛い石仏。村人からは歯痛止めの仏様として親しまれている。

「桝形茶屋つがるや」
街道が国道と合流する所、昔の桝形の右に桝形茶家のつるが屋がある。
「国道との合流点の番所」
振り返って見ると合流地点、街道の左手に番所のような物が建てられている。
「つがるやの漆喰壁」
国道の向かいからつがる屋を見る。表の二階壁面に枡の形とつがるやの屋号を漆喰塗りで浮き出して描かれている。

「つがるやの全景」
壁の右手は出桁で二階を前に突き出す造りとなっている。
追分から小田井へ
「北国街道の追分・分去れ」
桝形から100m程行くと分去れ、右へ分かれるのが北国街道・善光寺道の追分。この追分が宿の名前の由来となった。

「分去れの碑群」
ここには色々な碑などが立っている。
森羅亭万象(平賀源内)の歌碑、寛政元年(1789)建立。
世の中はありのままにぞ霰ふる かしましとだに心とめねば
道標 干時延宝7巳未(1679)建立。
常夜灯
手水鉢様道しるべ石
さらしなは右みよしのは左にて 月と花とを追分の宿
他の3面に各地への里程が記されている。
石地蔵坐像 子供を抱いた姿、マリア地蔵とも呼ばれる。
観音立像 安永6年(1777)建立。
「追分からの浅間」
分去れを見てすぐに国道から左に分かれる。やや下りながら西軽井沢へと向かう。振り返ると浅間の姿が大きく、頂上の雲が切れ煙の上がるのが見える。
「西軽井沢からの浅間」
雨が殆ど止んだ。この辺りから見る浅間の景色は最高。
「御代田の一里塚入口」
クリやアカシア、カラマツ、アカマツ等街道脇の色々な木々を見ながら歩く。久保沢川を渡ると御代田。人家が目立つようになったところ、右手に一里塚入口の標柱。
「御代田の一里塚」
右へ少し入った民家のすぐ際に大きな枝垂桜、これが御代田の一里塚。この桜は日露戦争の戦勝記念に植えられたとか。
「御代田の一里塚」
街道から20数m離れた民家の裏手にあるが、これは寛永2年(1625)と12年(1636)に街道の大改修が行われ、道筋が移動し塚が取り残された為である。

「御代田の一里塚」
大きすぎて、近すぎて、塚と桜を上手く捉えることが出来ない。
「御代田からの浅間」
雨が完全に上がって青空が見えるようになってきた。
しなの鉄道を地下道でくぐり栄町へ。ここを直進しひたすら歩く。荒町を通り小田井へ向かう。

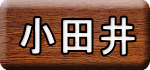
中山道第二十一宿 小田井宿
所在地 長野県北佐久郡御代田町御代田
最寄駅 しなの鉄道御代田駅
本陣1、脇本陣1、旅籠5、総人口319、家数107
岩村田へ 1里7町(4.7㎞)
「御嶽信仰碑」
小田井に入る信号の手前右に、御嶽信仰の碑が幾つか立っている。
「中山道小田井宿跡入口」
街道の右に小田井宿跡入口の白い標柱。
「街道らしい建物」
宿に入るとすぐ左に宿場らしい建物がある。
「上の桝形」
左手に宿の案内板。この前で道がやや右にカーブしている。これが小田井の上の桝形でここからが宿の中心となる。

「小田井宿本陣安川家」
宿の右手門構えの家が安川本陣跡、建物は宝暦6年に建て直されたもので、和宮降嫁に際し改修された。

「小田井宿本陣安川家」
当時の母屋は切妻造りで屋根は板葺き石置屋根だったとか。今は亜鉛引き鉄板葺きになっている。
「小田井宿説明板」
同じならびに小田井宿の解説板がある。
「上の問屋安川家」
本陣の先右手にある堂々とした建物が上の問屋安川家。江戸後期に建てられた。

「上の問屋安川家」
街道に面した格子を外すと板の間が間口一杯に広がり荷物を扱えるようになっている。
「脇本陣跡」
宿の左手にすはま屋又左衛門脇本陣跡の標柱。建物は現存していないが屋敷図は保存されているとか。
「古い建物」
宿の右手、格子と白壁のコントラストが美しい。
「古い建物」
宿の左手、

「古い建物」
同じ建物の右側部分。
「下の問屋尾台家」
宿の左手、白壁に貫のある長屋門が下の問屋の尾台家。
「下の問屋尾台家」
大きな切妻造りの母屋は無住で荒れている。何とか早く保存の手を。
「下の桝形」
旅籠だったような家が何軒かあって、道は左にカーブする。ここが下の桝形である。
小田井から岩村田へ
「古い民家」
街道の右手に旅籠らしい建物。二階に手摺欄干が付いている。
「皎月原」
下宿を過ぎ荒田入口信号で県道と合流。それからしばらく歩いて右手蓼科製作所の前あたりに茂みが有る。その中に標柱と解説板。
伝説によると、6世紀用明天皇の頃、皎月という官女がこの地に流された。白馬を愛しここで乗り回していたが、実はその馬は天の龍馬で、皎月は空を飛び吾妻山の上で『我は白山大権現なり』と言って岩の中に入ってしまった。

「皎月原からの浅間」
振り返ると浅間の峰が大きく見える。しかし山頂の雲がなかなか取れない。
「鵜縄沢端の一里塚」
桃の里横根入口信号交差点の左先にこんもりとした茂みがある。これが一里塚跡。ここも改修により道筋が移動し取り残されて古い姿が残ったもの。
「鵜縄沢端の一里塚」
交差点の反対側から全体を眺める。この先で上信越自動車道を跨ぐ。右に佐久インター。郊外型のお店があつまっており、その中のレストランで昼食を取る。
「りんご畑の向こうに見る浅間」
街道脇にはりんごが熟れて、真っ赤な実を付けている。

「石仏・石碑群」
街道の左手、千手観音の大きな石碑をはじめ石地蔵や多くの石仏が集められている。
「住吉神社」
街道の左手、石垣を上がったところに住吉神社の大きな石碑と、樹齢700~800年と言われる大ケヤキがある。

中山道第二十二宿 岩村田宿
所在地 長野県佐久市岩村田
最寄駅 JR小海線岩村田駅
本陣0、脇本陣0、旅籠8、総人口1,637、家数350
塩名田へ 1里11町(5.1㎞)
「善光寺道道標」
住吉神社からすぐ道路の向かい側の歩道上に従是善光寺道の大きな道標。神社とこの道標の間辺りに江戸方の桝形があった。
「白壁の屋敷」
岩村田には本陣、脇本陣が無く、旅籠も僅か8軒のみ。宿場と言うより内藤氏16,000石の城下町で米の集散地であった。そのため宿場を想わす建物は無く、このような屋敷が目に付く。
「宿の中心・本町通り」
宿の中心部の本町通は商店街。

「本陣の代役を務めた龍雲寺」
宿の左に龍雲寺。本陣が無い為、止むを得ない場合にはこの寺が本陣の代わりを務めたと言う。
「西へ折れた宿場通り」
本町通りを相生町の信号交差点で右折する。町は急に寂れる。およそ100mで左ブロック塀の前に道祖神、ここが京方桝形のあったと所と言う。

岩村田から塩名田へ
「御嶽社と石神・石仏群」
岩村田の宿を出て、国道とJR小海線を渡る。街道が大きくカーブする所に御嶽社と多くの石神、石仏が集められている。
「相生の松の碑」
右手に岩村田高校、左手に浅間総合病院を見て進み、左にカーブしてすぐ右に曲がる所の左手に、相生の松とその碑がある。ここは皇女和宮の降嫁の折り野点が行われた所。
「八ヶ岳を望む」
左の展望が開け、八ヶ岳連峰が綺麗に見える。
「浅間を望む」
右後方には稲穂の向こうに浅間の山並み、とにかく見晴が良い。

「稲荷神社と平塚の一里塚跡」
濁川の橋を渡ると右手に石の鳥居、奥に稲荷神社。右の住宅の前庭と道路の向かいに一里塚が有ったが、今は何の印しも無い。
「りんご畑を行く」
左にりんご畑を見て平塚の集落へと向かう。
「平塚の民家」
平塚の集落には落着いた町並みが残っている。

「**神社」
根々井塚原の集落に入ってすぐ右手に神社。何れの神様がおわす神社か失礼ながら記録できず。
「根々井塚原の民家」
この集落にも立派な屋敷があり、落着いた町並みを残している。
「妙楽寺」
左手に妙楽寺。
「新道と旧道の追分」
妙楽寺の先で旧道と新道が分かれる。左の旧道は今舗装工事中で通行出来ず。止む無く新道を行く。
「駒形神社」
再び旧道と合流した先、右手に駒形神社。望月の牧の鏡を祭ったお宮で、本殿は文明18年(1486)の建築で国の重要文化財に指定されている。
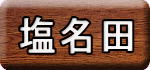
中山道第二十三宿 塩名田宿
所在地 長野県北佐久郡浅科村塩名田
最寄駅 JR長野新幹線佐久平駅
本陣2、脇本陣1、旅籠7、総人口574、家数116
八幡へ 27町(2.9㎞)
「塩名田宿標識」
駒形神社を過ぎ、東電の導水管を右下に見て、やがて塩名田の変形5差路の信号交差点に着く。交差点の手前左に中山道塩名田宿の標柱。
「塩名田変形五差路の交差点」
この正面の道が中山道、ここから塩名田宿に入る。
「丸山家本陣・問屋跡」
宿の中ほど右手の、少し奥まって建つ妻入切妻造り、二階建てせがい造りと言う豪壮な家が丸山家本陣、宝暦4年(1754)の建築、道路脇生垣の間に塩名田宿本陣・問屋跡の標柱。大きな鬼瓦に丸山の字。

「宿の中心部・中宿」
宿の中心部、出桁造りの家が並ぶ。
「二階の出格子が見事」
二階の出格子が白壁と調和して美しい。是まさに日本建築の美。
「えび屋豆腐店」
逆光で上手く撮れなかったが、えび屋豆腐店の並びは古き時代の香りを残している。
「えび屋豆腐店」
振り返って見る。卯建に白壁、お婆さん達の立ち話がこの風景にぴったり。
「桝形」
このカーブが桝形で、ガードレールの右から下に下りると川原宿。
「川原宿」
千曲川へと道は下って行く。

「川原宿の民家」
古い建築様式が良く判る。
「千曲川舟繋ぎ石の解説板」
街道が千曲川に突き当たった所に標柱と解説板。

「舟繋ぎ石」
千曲川は暴れ川で度々橋が流失した為、明治6年(1873)から20年間は船橋が用いられた。この石は船橋の台船を繋ぎ止めておく為の石で、綱を通す穴が開いている。
塩名田から八幡へ
「千曲川に架かる中津橋」
千曲川に架かる中津橋を渡って宿を出る。
「中津橋を渡る」
中津橋の歩道橋。
「中津橋から浅間遠望」
中津橋から右手を眺める。長野新幹線の向こうに浅間が見える。
「御馬寄の民家」
千曲川を渡ると御馬寄の集落、上り坂を行く。右手に街道らしい民家。
「大日如来」
浅科小学校歩道橋から右へ分かれ段丘上に出る。街道の右手、帽子に前垂れを着た大日如来像が素朴な表情で座っている。その背後には浅間がくっきりと見える。前の石柱に明和8年辛卯(1771)と彫られているので、その頃のものか。

「一里塚跡の標柱」
大日様から程無く右手に、一里塚跡の標柱。是が御馬寄の一里塚。
「下原の民家」
下原の集落に入る。右手に朽ちかけた民家。風情あり再建出来ればなー・・・と思う。
「八幡宿の家並を望む」
下原からは下り坂、左前方に次の八幡宿が一望出来る。


中山道第二十四宿 八幡宿
所在地 長野県北佐久郡浅科村八幡
最寄駅 JR長野新幹線佐久平駅
本陣1、脇本陣4、旅籠3、総人口719、家数143
望月へ 32町(3.5㎞)
「八幡神社」
中澤川を越え、やや左にカーブすると右手に宿名のもとになった八幡神社。貞観元年(859)創祠と言われ、旧本殿高良社は国の重要文化財に指定されている。神社の鳥居前が江戸方桝形で、ここからが八幡の宿。
「八幡宿の中心部」
人通りは殆どなく、向こうから町営のマイクロバスが走ってくる。
「旧問屋兼名主依田家」
八幡東交差点手前左手に依田家の屋敷。規模は大きいが軒の庇は歪み痛みがひどい。
「中山道八幡宿本陣跡」
宿の右手に本陣小松家の門が残っており、前に標石が立つ。この門は文化元年(1804)のもの。

「白壁と格子が美しい民家」
宿の左手に白壁と二階の格子が美しい民家がある。それなりの旧家であろう。
八幡から望月へ
「百沢集落へ向かう」
八幡入口で宿は終わる。その後旧道は右に分かれ、再び国道と合流し布施川を渡ってから右に分かれると百沢の集落。
「百沢の町並み」
用水の水音が心地よく聞こえる、落着いた町並みで、街道筋らしい魅力的な雰囲気に包まれている。
「百沢の道祖神」
集落の西の外れの右手に道祖神。ここのは宮廷貴族の装束をした男女が酒を酌み交わす華麗な祝言像で、通常は日本神話の神々であるのに宮廷貴族風であるところが非常に珍しい。
「望月宿案内と道祖神」
国道の右手に、中山道望月宿、石仏の里の案内標示が有り、そばに大きな村おこし道祖神。これを横目に古い道をたどる。
「中山道瓜生坂の一里塚跡」
国道を横切り、畑の中の道から望月トンネルの上を越え旧国道に出ると、左手に一里塚跡。中山道一里塚跡の標柱と、解説板が立っている。
「中山道瓜生坂碑と百万遍念仏塔」
一里塚のすぐ先、左手に中山道瓜生坂の大きな石柱とそばに百万遍念仏塔と石仏がある。
「坂を下る・望月宿遠望」
百万遍供養塔から一気に崖を下る。望月までの下りが長坂。坂の向こうに望月の宿が見える。
「中山道長坂石仏群」
長坂の途中右手に馬頭観音や道祖神、百万遍供養塔、御嶽講など数多くの石神、石仏や碑が集められている。
「中山道長坂石仏群」
石仏群の標柱と多くの石仏たち。
「鹿曲川の長坂橋を渡る」
長坂を下ると鹿曲川。その長坂橋を渡ると望月宿の桝形に入る。
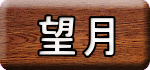
中山道第二十五宿 望月宿
所在地 長野県北佐久郡望月町
最寄駅 JR長野新幹線佐久平駅
本陣1、脇本陣1、旅籠9、総人口360、家数82
芦田へ 1里8町(4.8㎞)
「江戸方桝形に向かう坂にある家」
橋を渡り坂を上った所が望月宿江戸方コの字桝形で、その途中にも出桁造りの家がある。
「江戸方桝形の家」
門構えの大きな家。
「江戸方桝形の家」
二階が塗り壁の家。
「中山道旅籠山しろ屋」
宿に入ってすぐ左にバスターミナル。その先左、坂を上ると役場。宿がやや左に折れる。折れたその先右手に中山道旅篭山しろ屋の看板を下げた旅館山城屋。入口のガラス戸が無かったら昔の旅篭そのまま。

「木造三階建ての井出野屋旅館」
その向かい宿の左手に木造三階建ての洋風館井出野屋旅館。大正5年(1915)の建築。映画「犬神家の一族」で金田一耕介が泊まったのはこの旅館。いかにもその雰囲気。玄関には『電話十六番』とあるのが郷愁を誘う。今晩はここでお世話になる。

「ますや洋品店」
宿の左手、白い蔵と二階の連子格子、古い商家の姿をそのまま伝えている。
「民家」
二階の手摺が旅籠屋風。
「民家」
出桁造り、二階の連子格子が当時の宿場の様子を偲ばせてくれる。
「本陣兼問屋跡の望月町歴史民族博物館」
宿の左手の歴史民俗博物館と右隣の大森小児医院が望月宿の本陣兼問屋で庄屋をも兼ねていた大森家の跡である。その前には高札場もあった。

「脇本陣兼問屋鷹野屋」
本陣の向かい、宿の右手には脇本陣兼問屋だった鷹野家がある。
「旅籠大和屋」
宿の右手にある大和屋の看板は江戸中期の遺構を残す問屋兼旅籠、幕末には庄屋でもあった真山家で、明和2年(1765)望月宿大火の直後に建てられた望月最古のもので国の重要文化財に指定されている。

「春美屋の下駄の看板」
宿の左手、軒先から大きな下駄が下がっているのは、かつて下駄屋であった春美屋の看板。
「望月宿の町並み」
宿の外れより中心部を振り返って見る。
望月の宿をひととおり見た後、本陣跡にある望月町歴史民族資料館を見学し、4時40分にあらかじめ予約しておいた井出野屋旅館に入る。 ここは大正5年(1915)に建築された木造三階建、黒光りする大黒柱に障子のはまった日本間で、映画「犬神家の一族」のロケに使われたという。中には関係者のサイン色紙等が額に入れていっぱい飾られている。さっそく風呂に入って汗を流し、6時に食事、馬刺しや朝鮮人参の天婦羅等が出て結構お値打ち。一杯飲みながら巨人長嶋監督退任のテレビニュースを見る。天気予報では軽井沢で今朝の最低気温10℃、明日は1℃まで下がるとの事、天気は良さそう。何もする事無く早々に床に入る。
50,783歩
沓掛~望月 25.5㎞
ページ公開 平成15年1月20日
ページ改良 平成22年11月1日
写真追加 平成22年11月11日
表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ
|