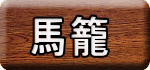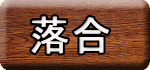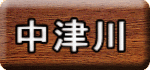|


「馬籠宿脇本陣資料館」 宿の中程、右手に馬籠脇本陣資料館があり、前に『馬籠宿脇本陣跡』の説明板と山口誓子の句碑がある。八幡屋こと蜂谷家脇本陣跡で、建物は明治28年の大火で焼けたが蜂谷家の古文書や民具、木曽五木等が裏手の資料館に展示されている。八幡屋は馬籠で初めて酒を造ったという家で金貸しもしていた。初代から4代約100年書き継いだ覚書が藤村『夜明け前』の重要資料となった。 

「藤村記念館」 大黒家の隣が島崎本陣の跡。藤村の生家、島崎家は馬籠城主島崎監物の子孫で本陣、問屋を勤めかつては代官と呼ばれていた。黒板塀に冠木門、門の奥の白壁に藤村の言葉『血につながるふるさと・・・』。中に記念館と記念堂、裏には隠居所建物や井戸があり、博物館相当施設としなっている。以前に2度来ているので中へは入らず。向かいには観光案内所、隣には藤村長男経営に旅館四方木屋の出店、四方木屋民芸部がある。 


「桝形」 何度も見慣れた馬籠の桝形。ここから左へカーブしながら坂を下るのが新道で、真っ直ぐに石段を下りて左に折れるのが復元された旧道。下へ下る石段の右手には水車小屋、左上には常夜灯が立つ。 「桝形の水車と常夜灯」 正面に水車小屋、右には石組みの上に常夜灯が立っている。 「桝形から見上げる」 中山道が急な山の尾根を通っていることから『坂に開けた宿』で、この桝形は城郭を想わせる。水利が悪く風が吹き上がるため、しばしば大火に見舞われ、なかでも明治28年と大正4年の大火で江戸時代の民家はほとんど焼失した。 
「車屋坂碑と桝形の解説」 桝形で直角に折れた先が急坂で、車屋坂の標石が立っている。左手に馬籠の宿場と桝形の詳しい解説板がある。


「庚申塚」 左に庚申塚や多くの石仏がある。 「諏訪神社」 集落の中程左手に諏訪神社。 
「島崎正樹の碑」 諏訪神社の鳥居に傍らに『島崎正樹翁碑』。『夜明け前』の青山半蔵のモデルである正樹を記念するもので、次男の広助の奔走により明治45年に立てられた。 
「子規の碑」 中のかやバス停前右手に正岡子規の句碑がある。 桑の実の木曽路出れば穂麦かな 子規 「中津川盆地を一望」 子規の句碑のあるところから右手に視界が広がり、落合、中津川方面が一望出来る。 


「一里塚古跡の碑」 塚のそばに一里塚古跡の碑と解説板がある。 「中山道、中津川宿・落合宿、石畳の解説板」 約100m程でバス道は右へ分かれ、右手に大きな解説板がある。ここから石畳道となり木立の中に入ってゆく。左の碑には『岐阜県中山道落合石畳』、難所と言われた十曲峠で長野県と岐阜県の県境である。 
「落合の石畳」 素晴らしい石畳、カーブの先、更にそのカーブの先へと石畳が続く。中山道の中でも最高の景色である。 

「医王寺」 石畳を抜けると中山の集落、左手に瑠璃山医王寺がある。本尊薬師如来は行基の作と伝えられ、虫封じの薬師として信仰を集め、江戸時代には旅人相手に『きつね膏薬』を売っており、刀傷に特効があったという。 
「芭蕉句碑」 医王寺の境内に嘉永6年(1853)建立の芭蕉句碑がある。 梅が香にのっと日の出る山路かな 芭蕉 この辺りで完全に雨が止む。日傘代わりに差してきた傘も畳んでリュックにしまう。あ~良かった。 「落合川の下桁橋」 医王寺から道なりに急坂を下ると、落合川に架かる下桁橋を渡る。 「落合川」 下桁橋から見る落合川、上流に砂防堰堤があり、簾のように涼しげに水が落ちている。 
「道標」 橋を渡って上り坂、途中に道祖神や『右飯田道・左御嵩道』の道標や『右神坂ヲ経テ飯田町ニ通ズ』の道標が立っている。

「上の桝形」 県道を横切って、左にカーブしながら坂を上ると桝形で、角に常夜灯がある。 

「落合宿本陣跡」 向かいの門構えの家が本陣の井口家で問屋、庄屋も兼ねていた。文化12年(1815)の大火の後に再建された中山道でも現存する数少ない本陣建築。この門は加賀藩から火事見舞いとして贈られたものという。門前に『落合宿本陣』の標石と『明治天皇落合御小休所』の石碑が立っている。 

「桝形と道標」 右手善昌寺があるところが下の枡形。今、宿の道はそのまま国道19号に繋がっているが、昔はここで行き止まり、左に折れて中津川へと向かった。左の角に大きな石の道標『左至中仙道中津町1里』とあり大正11年の建立。道標にしたがって左折する。 

「おがらん四社の鳥居」 神社の名前が『おがらん四社』、おがらんとは小高い所の意、愛宕神社、山之神神社、天神社、落合五郎兼行神社の四社で、ここは落合五郎兼行の館跡。 「与坂立場跡」 道なりに進むと今度は国道19号をくぐって再び南側へ、ここからは急な上り坂。与坂を上がる。こんな坂道で暮らす人はどの様にしているのだろうか。お年寄りや子供達、車を利用出来ない人達の苦労を思う。坂を上りきった所に立場跡の碑。昔は越前屋という茶屋があり餅を売っていた。 

「覚明神社」 また坂を上って右手、玉石垣の上に覚明神社。覚明とは木曽御嶽講の開祖で、天明5年(1785)木曽御嶽を開くために中山道を通った覚明がここにあった茶屋に泊ったのを記念して建てたという。  「地蔵堂石仏群と枝垂れ梅」 再び坂を下ると地蔵堂川の手前左手に地蔵堂の石仏群。庚申塔や色々な石仏が集められ大きな枝垂梅もある。この辺り急な坂の連続、上り下りが激しい。どうしてこんなルートになったのか。家内はダラダラ歩くとかえって疲れるといって早足で歩くが、大丈夫かとちょっと心配。 「秋葉山常夜灯」 坂を上がって住宅地に入り、国道を地下道でくぐる。間もなく左手に秋葉大権現の常夜灯。 「尾州藩白木改番所跡」 続いて右手に番所跡の碑。ヒノキ等木曽五木を取り締まった役所の跡。 
「芭蕉句碑」 坂を下る途中左手に旭ヶ丘公園があり、藤村『夜明け前』に別名で登場する本陣、問屋、庄屋などを勤めた中津川宿の旦那衆の句碑や芭蕉の句碑などがある。 山路来て何や羅遊かし寿み連草 芭蕉 この辺りを茶屋坂と言い、前方に中津川宿を見下ろすことができる。


「格子造りの民家」 宿場らしくなってきた。 
「前田青邨画伯生誕之地碑」 右手に『前田青邨画伯生誕之地』と刻んだ銅版のはまった石碑がある。 「大正の蔵」 少し行った左手に間家の大正蔵がある。東濃一の豪商と言われた間家の屋敷内に有った倉庫の一つで市の有形文化財。中津川商人の資料や宿の資料が展示されている。 「中津川宿往来庭」 右手、向かいに街の博物館の往来庭。 
「四ツ目川橋」 四ツ目川に架かる真新しい橋四ツ目橋を渡る。宿の中央を流れる川でよく氾濫し今の川筋が四番目と言う。宿場の橋らしくデザインされている。ここから先が本町通で宿の中心。 
「秋葉神社」 橋を渡ったすぐ左手に小祠。昔は街道の中央に防火の為の用水が作られていて、その東端に秋葉山が祀られていた。 「中津川宿脇本陣跡」 左手NTTビルの横に『中津川宿脇本陣跡』の標柱。 
「中津川宿本陣跡」 右手、脇本陣跡の向かいに『中津川宿本陣跡』の標柱と本陣見取り図と解説板がある。この宿には本陣、脇本陣、庄屋と問屋場2ヶ所が置かれていた。 


「十八屋」 横町右手、川上家の先に十八屋間家。江戸中期に建てられた家で、皇女和宮のお供も泊ったという。 

「式内恵奈山川上道碑」 横町から下町に曲がる所に立つ道標で、慶応元年(1865)建立。延喜式内社恵那神社へ向かう道を川上道(かおれ道)と言い、細い野道でであったと言われている。 「卯建のある家並」 右に曲がった下町の左手に卯建の上がった家が並ぶ。 
表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |