|
中山道ウォーク その15 平成15年3月28日(金) 高宮から武佐まで 国連で散々揉んだあげくに米英が見切り発車。イラク攻撃を開始してから早8日が経った。短期終結の予想を裏切って長期戦の様相を示している。戦争が長引けば世界経済に悪い影響を与えるし、増してや日本経済は3月の年度末を控えている。株や円の値動き次第ではパニックが起らないとは限らない。何とか早く終わって貰いたいものだ。 でも、自然はそんな事とは関係なく春が訪れ、花が咲いた。今年の桜は例年より3日早いとのこと。 3月28日(金) 今朝も家内にJR二川駅まで送ってもらって出発する。前回と同じ電車の二川発7時35分に乗車して豊橋へ。豊橋で乗換えるのだが、今日は平日の為ダイヤが少し違っていて7時45分発特別快速の大垣行きに乗車する。大垣で9時16分発米原行きに乗換え、さらに米原で9時56分発姫路行きに乗換え彦根へ。彦根からは近江鉄道で2駅目の高宮まで行くのだが、10時代は10時27分発貴生川行きの1本だけしか無い。仕方なくそれを待って高宮へ、10時34分高宮着。駅でトイレを済ませ装備スタイルを整え出発する。 今日は暖かく風もなく快晴で、車窓から岐阜あたりまでは咲き始めた桜が見えていたが、近江路に入ってからは未だ見掛けていない。気候がだいぶ違っているようだ。 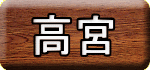 中山道第六十四宿 高宮宿 所在地 滋賀県彦根市 最寄駅 近江鉄道本線高宮駅 本陣1、脇本陣2、旅籠23、総人口3,560、家数835 愛知川へ 2里(7.9㎞) 「高宮宿の旧旅籠」 近江鉄道高宮駅からおよそ300mで宿の道に出る。そこから一路愛知川へと向かう。宿の左手、布総の手前に格子造りの家があり、その前に竹の格子で目隠しがされている。鳥居本でも見掛けたのだが、これはこの辺りの旅籠の特色だとか。  高宮から愛知川へ 「産の宮の井戸」 むちん橋を渡って高宮の宿を出る。法士(ほうぜ)町の右手に瓦葺きの屋根に覆われた井戸があり、長い由緒書きが掲げられている。文和5年(1356)足利義詮の側室がここで男児を出産したがその子は死没、生母は悲しんで尼となり庵を結んでその子の菩提を弔った。庵の北に祀ったのが産の宮。 
「街道らしい風景」 葛籠(つづら)町の左手、カーブする街道に沿って白壁土蔵に黒板塀の古い民家がある。庭からマツの木が聳え典型的な街道の風景、何時までも残しておきたい風景だ。 
「モニュメント」 少しばかりの松並木があり、その先左手に再び彦根市のモニュメント。3本の石柱の上に麻の原料を運ぶ女性、宿場へ向かう旅人、荷を運ぶ人足のブロンズ像が乗っている。石柱のこちら側には『またおいでやす』、向こう側には『おいでやす彦根市』とある。  「阿自岐神社の鳥居」 次の交差点を右に行くとJR河瀬駅、左に行くと近江鉄道尼子駅。直進して出町の集落を過ぎると右手に1対の常夜灯と石の鳥居があって右側に『縣社阿自岐神社』の大きな石柱がある。この奥にある神社が百済渡来人の阿自岐氏の邸宅跡で、日本最古の名園があるという。 
「近江商人日仏貿易の祖薩摩治兵衛の碑」 豊郷町最初の集落が四十九院、僧行基が四十九の寺院をこの地に建てた所から来た地名。その左手に大きな石碑がある。奥には先人を偲ぶ館が、左手には四十九院の一つの唯念寺と恵林寺とがある。 
「豊郷小学校」 左手に有るのが校舎の保存や町長のリコールで話題となった豊郷小学校。昭和12年丸紅の専務古川鉄次郎の寄贈で建てられた県下初の鉄筋の小学校で、当時は東洋一と言われた。今は建築用の塀に囲まれ前には仮設校舎が建っている。市民運動の集会があったのか校門の前で受付や募金が行われている。 「一里塚の郷石畑碑」 小学校の先、左手の八幡神社の脇に『中山道一里塚の郷石畑』の碑と、『石畑間の宿』の碑がある。 
「一里塚の有った町役場付近」 町役場前の信号機のある辺りに一里塚があった。一里塚跡の標柱はこの先の又十屋敷の玄関脇に移されている。 「くれなゐ園」 役場のすぐ先、左手に公園のように整備された所が『くれなゐ園』で、丸紅の関係者が伊藤忠、丸紅の創始者伊藤忠兵衛(初代)の功績を称えて作ったもの。中央には氏の肖像が嵌め込まれた碑がある。 
「伊藤長兵衛家屋敷跡」 隣の空き地に『伊藤長兵衛家屋敷跡』の大きな石碑がある。伊藤長兵衛は本家初代忠兵衛の兄で丸紅商事の初代社長で豊郷病院を設立した。 「伊藤忠兵衛屋敷跡」 左手門構えに長い黒板塀の屋敷が伊藤忠兵衛の屋敷の跡。ここで丁度昼になった。屋敷跡の向かいに食事の出来るお店が有ったので昼食とする。旧道を歩いているとなかなかうまい具合に見付からないものだが、今日はラッキー。  「天稚彦神社」 右手奥に鳥居が見えるのが天稚彦神社でその隣に大きな屋敷がある。白と黒のコントラストが美しく赤いレンガの煙突がそれを引き立てている。表の通りを行くだけではどんな仕事をしているのか判らない。 
「金田池跡」 右手に板石組で井戸が再現されているのが金田池。この北にかつて金田池と称する湧水があって、この地の田畑を潤し、街道を旅する人達の喉を潤してきた。側に池の解説と『水の香る郷四ツ谷』の碑と『西沢新平家邸跡』の碑がある。 
「又十屋敷」 下枝の集落に入ると右手に『又十屋敷』(豊会館)の大きな看板が目に入る。豪商藤野喜兵衛の屋敷跡を明治百年記念資料館と民芸展示館として公開している。藤野喜兵衛は北海道で漁業や廻船業で財をなした。又十は当時の屋号。玄関の右手に『中山道一里塚跡』の標石が立っている。 
「江州音頭発祥地碑」 右手四十九院の一つ千樹寺の入口に『江州音頭発祥地』の大きな碑と『伝統芸能扇踊り日傘踊り中山道千枝の郷』の碑と、『観音堂(千樹寺)と盆踊り、江州音頭発祥の起源』の石の解説板がある。  「石部神社」 宇曽川の歌詰橋を渡って愛知川町に入る。渡ってすぐ左、民家の奥に小さな祠が乗った塚(円墳)が見える。これが平将門の首塚。写真が撮りづらかったのでパスする。石橋の集落の外れ左手に『式内石部神社』の石の鳥居と標柱がある。鳥居の向こう遥か先まで石灯籠が並んでいる。 
「愛知川宿入口の追分」 沓掛の交差点の先で道が二又に分かれる。左へ行くと近江鉄道本線愛知川駅。右の道が旧道。その中央に豊満神社の道標が立っている。 「河脇神社」 右手の愛知川小学校を過ぎると中宿の集落で、右手に河脇神社がある。 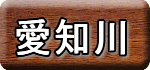 中山道第六十五宿 愛知川宿 所在地 滋賀県愛知郡愛知川町 最寄駅 近江鉄道本線愛知川駅 本陣1、脇本陣2、旅籠28、総人口929、家数199 武佐へ 2里半(9.8㎞) 「中山道愛知川宿のアーチ」 間も無く街道の頭上に冠木門形のアーチが掛かる。中山道愛知川宿の看板である。  「土蔵造りの料亭」 左手には黒板塀で土蔵造りの料亭近江商人亭がある。 「愛知川宿入口の碑とお地蔵さん」 右手には『愛知川宿北入口』の標石があり、横には石の地蔵さんが20体余り並んでいる。それぞれに可愛らしい前掛けが着せられている。 
「宿中ほどのポケットパーク」 宿中央交差点の左先にポケットパークがあり、『中山道愛知川宿』の碑と、廣重の『木曽街道六拾九次之内恵智川』の浮世絵と、『むちん橋の由来』、そして黒い『書状集箱』がある。書状集箱はポストで現役である。 
「愛知川宿の家並」 道は左へ僅かにカーブし、白壁と格子造りの家がある。春の日の昼下がり、のんびりとして時間もゆっくりと進みそう。  「寶満寺標石」 右手にガラスケースに入った宝満寺の石の標識がある。このように保護された標識や道標を見るのは初めての経験である。 
「八幡神社前の高札場跡碑」 右手に1対の石灯籠と石の鳥居のある八幡神社。その左脇に高札場の標石がある。 「本陣跡」 右手にある洋館が愛知川宿の本陣跡であるとするガイドブックが有るが、現地には何も標示がされていない。愛知川宿の本陣は西沢家、建坪142坪(約469㎡)の門構え、玄関付きであったと言う。 
「脇本陣跡」 すぐ先の小さな洋館の前には『脇本陣跡』の標石が立っている。どうして本陣跡の標識が無いのだろうか。脇本陣は藤屋で建坪131坪(約432㎡)やはり門構え、玄関付きであった。  「問屋場跡」 左手の路傍にぽつりと『問屋跡』の標石が立っている。問屋の跡は割烹三角屋本店になっている。 「明治天皇御聖跡碑が立つ竹平楼」 左手の先、宿の外れ近くに、黒板塀門構えの屋敷があり、右玄関脇に『明治天皇御聖跡』の大きな碑が立っているのが料理旅館竹平楼。中には明治11年(1878)御小休のときの玉座が残されているという。  「不飲橋と宿出口にあるアーチ」 不飲川の不飲橋を渡ると、『中山道愛知川宿』のアーチがあり、ここで宿が終わる。この川、不思議な名前の川であるが、これは平将門の首をこの川の源、野間津池で洗ったために池の水が血で濁り不飲川と呼ばれるようになったとか。アーチをくぐると右からの国道8号線と合流し左へと進む。 
愛知川から武佐へ 「一里塚跡」 国道と合流してすぐ右手、駐車場の奥に一里塚跡の標石がある。側に最近では見掛けなくなった井戸の手押しポンプがある。懐かしいな~。 
「愛知川むちん橋の説明と常夜灯」 国道を行くとやがて愛知川の御幸橋に至るが、橋の左手前に祇園神社があり、その前に大きな常夜灯とむちん橋の解説板がある。この常夜灯は対岸のものとで一対になっている睨み灯篭で、弘化3年(1846)の建立。この橋も仮橋だったのを天保2年(1831)宿場商人の寄付で常設の橋となった。渡り賃を取らなかったのでむちん橋と言われた。  「愛知川の御幸橋」 明治11年(1878)天皇行幸に際し馬車で通れるように新設したので御幸橋となり、現在のものは昭和36年(1961)に架けられた。対岸までけっこう長い。 
「対岸の常夜灯」 橋を渡って国道から左折、堤防上を進み近江鉄道の踏切を越えると間も無く右手に常夜灯がある。これが川の両側で対になっているもの。 
「東嶺禅師御誕生地碑」 川を渡ると五個荘町、常夜灯で右に曲がり小幡の集落へ向かう。やがて右手に有るのが『東嶺禅師御誕生地』の碑。禅師は享保4年(1719)にこの地で生まれ駿河の白隠に師事し、禅の道を極めた。 「古い民家と近江鉄道踏切」 街道を進むと間も無く近江鉄道の踏切。この辺り古い民家と新しい民家が混在していて、昔の藁葺き屋根をそのままトタン葺きにした家がある。 「御代参街道道標」 小幡の集落をしばらく行くと、左手ななめ前方に入る道の角、民家のフェンスとガードレールに挟まれて古い道標が立っている。この道が伊勢参宮道、御代参街道とも言われる道で、道標は享保3年(1718)の建立で『右、京みち』『左、いせ、ひの、八日みち』と彫ってある。  「ポケットパークの常夜灯」 右にカーブする左手にポケットパークがあり、『大神宮』と彫られた背の高い常夜灯が立っている。その右手には正眼時がある。 「藁葺き屋根の家」 そのすぐ先右手には藁葺き屋根の家がある。 
「ポケットパークの中山道分延絵図」 橋を渡り国道から分かれてきた道に突き当って左折する。左には川、右には郵便局と役場が続く。川が街道から分かれてゆくその間のポケットパークに大きな五個荘あたりの『中山道分間延絵図』が設置されている。 
「西沢梵鐘鋳造所」 その先左手、板塀に囲まれた家が梵鐘の鋳造所。門の脇に釣鐘が置かれており、屋敷の中庭には幾つかの釣鐘が置かれている。このような光景を目にするのはめったに無い。 
「常夜灯」 左手背の高い台座の上に常夜灯がある。台座には『右京道』『左いせ道』とあり、道標を兼ねている。  「明治天皇北町屋御小休所碑」 左手のポケットパークには『明治天皇北町屋御小休所』の背の高い標石が立っている。 
「市田邸跡」 右手向いのコンクリートブロックに囲まれた家が市田邸跡。  「市田邸内の明治天皇御聖跡碑」 屋敷の左には『明治天皇御聖跡』碑と『説明』のパネルがある。  「大郡神社」 右手に鳥居が見えるのが大郡神社でこの辺り市田郷の産土神。神社はこの奥国道のさらに向こうにある。  「金毘羅大権現常夜灯と元ういろう屋の藁葺きの家」 次の十字路の右手先に金毘羅大権現の常夜灯があり、その後に落着いた藁葺き屋根の家がある。元ういろうを売っていたとか。  「こちらも藁葺きの家」 その向かい側、道の左手には用水が流れている。こちらにも藁葺き屋根の家がある。どちらも屋根は綺麗で手入れが行き届いている。今時材料も職人さんも入手が困難なのに、このように維持管理されているのは大変な苦労だろうと想像する。 「てんびんの里の近江商人像」 間も無く道は右から来た国道と斜めに合流する。その合流点に大きな石柱、『旧中山道』『てんびんの里』と彫られ、その上にてんびんを担いだ近江商人のブロンズの像が立っている。  「清水鼻の名水」 合流した国道から今度は右に分かれ繖(きぬがさ)山の裾を行く。右手に崖が迫っている辺りが立場の有った清水鼻。旅人が喉を潤した清水鼻の名水がある。ここに一里塚があった。  「常夜灯」 やがて道は左に折れる。すると右手に常夜灯がある。田圃の中を進み左手から来る国道と斜めに合流し、しばらく国道を行く。 「老蘇の森」 国道の左手にこんもりと繁った森が見える。これが老蘇の森。孝霊天皇5年(前286)、近江の国では地面が裂け水が湧き出て人が住めない所であった。石辺大連が神の助けを仰ぎマツ、スギ、ヒノキなどの苗を植えたらたちまち大森林になった。大連は百数十を過ぎても若く元気だったので人々は大連を『老蘇』(老いても元気)と呼び、この森を老蘇の森と呼ぶようになった。 「東老蘇の中山道標石」 国道の左手に中山道の標石と、鎌宮奥石神社の看板がある。旧道はそこから左へと進む。  「奥石神社東参道」 間も無く右手に奥石神社の東参道がある。 「木に吊るされた注連縄?」 神社境内から街道上に枝を伸ばした大木に、不思議な形の注連縄が吊るされている。どのようないわれが有るのだろうか。  「奥石神社」 神社に沿って右に回り込むように進むと神社正面に出る。この神社は延喜式内社で繖(きぬがさ)山を御神体とする原始的な神社。祭神は天児屋根命で中臣氏の祖神。安産授福の神とされている。  「鎌若宮神社」 東老蘇の集落を過ぎ右手の郵便局、左手の老蘇小学校を過ぎると西老蘇。右手に鎌若宮神社がある。  「東光寺」 続いて右手に東光寺。本尊の阿弥陀如来立像は平安時代後期の作で町指定の文化財である。 「泡子延命地蔵尊御遺跡碑」 近江八幡市西生来町に入りしばらく行くと、右手川の縁に碑があり、横のブロック塀にいわれが掲げられている。旅の僧が残した茶を飲んだ茶店の娘が身篭ってしまった。そして翌年に男児を産む。3年後にその旅僧が来たので、娘が経緯を告げると、僧は子供をふっと吹いて泡にしてしまった。同じ話が醒ヶ井宿の泡子塚にもある。  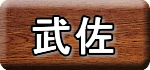 中山道第六十六宿 武佐宿 所在地 滋賀県近江八幡市 最寄駅 近江鉄道本線武佐駅 本陣1、脇本陣1、旅籠23、総人口537、家数183 守山へ 3里半(13.7㎞) 「武佐神社と東の高札場跡」 灌漑用の水路の橋を渡ると右手に武佐神社がある。神社の左手に木製の『中山道武佐宿』の看板と『高札場跡』の手作りの解説板がある。この宿場の標識や解説板は武佐小学校の関係者の手で作られたものとか。温か味があって街道を歩く我々にはとても役に立つ嬉しいもの。ありがとう。  「平尾家役人宅」 右手に平尾家役人宅。二階が低い塗篭壁で格子造り。街道の歴史を物語っている。  「広済寺前の明治天皇御聖跡碑」 左手には広済寺。『明治天皇御聖跡』に碑が立ち、奥の山門や石垣近くに『明治天皇武佐行在所』の碑もある。  「脇本陣跡」 右手斜め前に武佐町会館、その木戸門の右の柱に『武佐宿脇本陣跡』の看板が下がっている。ここが奥村家脇本陣の跡で、当時は建坪64坪(約211㎡)の建物があった。  「大橋家役人宅」 やがて宿の中心部に国道421号線の交差点がある。その左先に有るのが400年以上前からの商家で宿役人宅の大橋家跡。  「旅籠中村屋」 その隣中村屋の看板があるのが唯一今も営業を続けている元旅籠の中村屋。  「本陣跡」 中村屋の向いが下川本陣の跡。当時の門と土蔵が残っている。建坪は262坪(約865㎡)門構えの屋敷であった。右隣の郵便局が伝馬所跡と本陣の跡。郵便局の前にはここにも古いスタイルの黒い書状集箱が置かれている。  「松平周防守陣屋跡と愛宕山常夜灯」 宿の左手愛宕山の碑と常夜灯がある家が松平周防守の陣屋跡。  「八風街道道標」 左に入る道に文政4年(1821)の道標がある。『伊勢ミな口 ひの 八日市 道』とあり、この道は日野を経て水口から伊勢へ抜ける道と、八日市へぬける八風街道に通じていることを示している。  「愛宕山常夜灯と西の高札場跡」 その先右手に、ここにも愛宕山の碑と常夜灯がある。ここが西の高札場跡で宿の西の外れである。  「近江鉄道武佐駅」 中山道は近江鉄道武佐駅の横で踏み切りを渡り守山へと向かうが、今日の行程はここまでとし、ここから電車で近江八幡へ行く。 「近江鉄道の電車」 帰りはタイミング良くすぐに電車が来た。 今日は好天に恵まれ快適な街道歩きが出来た。ウメやモモの花が咲き、ハクモクレンが咲いているのが遠くから目に入ってくる。今までの木曽や美濃路とは少し雰囲気が違う。それだけ京に近付いて来ているからか。 豊郷、愛知川、五箇荘町は近江商人の地、活躍した当時を偲ばせるものが沢山残っている。今回特に目に付いたのは茅葺というか、藁葺というか、古い草屋根の民家が意外と多く残っているという事だった。苔むしたりせず綺麗な状態で、最近手入れをされたように見える。何時までも残っていて欲しいものだ。 近江鉄道武佐駅で今日の行程を終わる。帰りは非常にタイミングが良く2分と待たずに電車が来た。15時47分発に乗車、1駅6分で近江八幡へ。JR東海道線に乗換え15時59分発で米原へ、米原乗換え16時28分で大垣へ。大垣発17時03分の新快速で豊橋へ。豊橋に18時23分着。バスの時間まで本屋さんに寄って時間調整し18時50分発のバスで帰宅する。 ロケットH2A・5号機で日本初の偵察衛星の打ち上げに成功したとのニュース、周辺国を刺激しておかしい事にならなければ良いのだが・・・と思う。 34,172歩 高宮から武佐 17.7㎞
表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |