|
三日目 11月2日(金)
ホテルの部屋が暑く夜中何度か目が覚め、窓を開けて空気の入れ替えを行なう。朝6時、鶏の鳴声で目が覚める。諏訪大社に居るのかそれとも近くの家で飼っているのか久し振りに懐かしい声を聴いた。
起き掛け早々に温泉に入る。展望風呂からは諏訪湖が一望出来、東の山からは日が上ったところ。湖面が輝
いて今日も天気が良さそう。7時30分からのバイキング形式の朝食で腹ごしらえして準備OK。 8時塩尻に向け出発する。
下諏訪から塩尻へ
「魁塚」
枡形を出て国道20号を西へ向かう。駅前通を過ぎ、右に行く国道と分かれ直進すると左手に魁塚。偽官軍と言われて処刑された赤報隊の供養塔がある。

「春宮大通りの常夜灯と鳥居」
春宮大通りと交差する。右手に大きな常夜灯とその向こうに鳥居が見える。
「日限地蔵の春宮別当平福寺」
砥川を国道に出て富士見橋で渡り再び旧道に戻る。岡谷市に入ってしばらく行くと右手に『おひぎりさま』(日限地蔵)と呼ばれる春宮別当平福寺がある。
「伊那道道標」
長地東掘信号で伊那街道を横切る。角に『右中山道、左いなみち』の道標。
「東掘の一里塚」
生垣の続いた東堀を通り国道を横断、左岡谷自動車学校の道を行く。右手に丸い一里塚碑。江戸から56里目。

「四ツ場立場跡今井家茶屋本陣」
横河川の大橋を渡って今井の集落に入る。ここは四ツ谷立場跡で西の外れに茶屋本陣の今井家がある。

「茶屋本陣の建物」
江戸末期の本棟造り、上段の間や裏には厩も有ると言う。

「石船観音」
今井を抜けると丸山坂。岡谷インターを左に見下ろしながら上って行くと、右手石垣の上に石船観音。楓の紅葉がとっても綺麗。山手から流れ落ちてくる鳴沢の清水が別名金名水。和宮も明治天皇も渇きを癒したと言う。

「旧中山道の大石」
塩尻峠への坂道を登る。間も無く左手に諏訪七不思議の一つ、旧中山道の大石がある。昔から転がらずにここにあると言う。

「塩尻峠展望台より南を見る」
石船観音からの東坂を上りきって塩尻峠に到着。標高1,060.7m、午前10時、下諏訪から丁度2時間。展望台から南を見る。晴れていれば諏訪湖の向こう、左に八ヶ岳、正面に富士山、右に南アルプスが見えるはず。
「塩尻峠展望台より北を見る」
北を見る。塩尻の街の向こう、左に御岳、正面に乗鞍、右に北アルプス穂高連峰が見えるはず。雲が出て折角の眺望を楽しむ事が出来ない。
「浅間神社石祠」
富士山と向かい合って浅間神社の石の祠が祀られている。
「塩尻峠立場茶屋本陣跡」
峠から西に向かって下る。間も無く塩尻峠立場の茶屋本陣上条家、寛政年間(1789~1801)に建てられた本棟造り。今も奥に上段の間が残っている。前の軒にある柱が丸くなっているのは馬を繋いだ為とか。

「親子地蔵」
右手には大小2体の親子地蔵。そばに夜通道の標柱、片丘辺の美しい娘が岡部の男と逢うために毎夜通った道とか。
「東山の一里塚」
松井沢を越えると坂も緩くなり左手に一里塚。江戸から57里目。右手の北塚は開墾の為に失われている。

「犬飼の清水」
東山の集落を通り国道に出会うが、旧道は直ぐ右手へと分かれる。右手に犬飼の清水の標柱。とある公卿の愛犬が病気になりこの水を飲ませたら治ったと言う。
「新茶屋立場跡」
一旦国道と合流し再び分かれ、右の農道に入る。途中に新茶屋立場跡が有るはずだがどれだか判らない。
「柿沢の集落」
右手にみどり湖パーキングエリアを見て長野自動車道の上を渡る。柿沢集落に入ると庭木や植え込みの木々が紅葉の真っ盛り、一瞬見惚れてしまう。
「首塚」
右手に丸山が近付いた辺り、左に首塚の案内がある。案内に従って畑の中を入って行くと塚と碑がある。塩尻峠の合戦の戦死者を葬った跡。

「雀脅しの付いた本棟造りの家」
屋根に雀脅しの付いた本棟造りの旧家が何軒か目に入る。

「永福寺」
下柿沢信号を渡り、永福寺への道と分かれ直進し国道に合流する。右に見えるのが栄福寺、木曽義仲が信仰した駒形観音が伝わる。
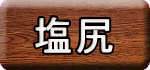
中山道第三十宿 塩尻宿
所在地 長野県塩尻市
最寄駅 JR中央本線塩尻駅
本陣1、脇本陣1、旅籠75、総人口794、家数166
洗馬へ 1里30町(7.2㎞)
「三州街道」
宿に入ると左手に三州街道の標石、ここから三河道や伊那街道とも呼ばれる道が分かれる。
「口留番所跡」
右に松本藩塩尻宿口留番所跡。この辺りが宿の東の外れか。
「古い民家」
左手に宿場らしい民家。
「元旅籠小野家住宅」
右手に『重要文化財小野家住宅2棟』の石柱の立っている家が、元旅籠いてふ家の小野家。

「塩尻宿中心部」
塩尻町信号が宿の中心。信号の右手前が小野家住宅、左手前が上問屋跡、右手向こうが下問屋跡と高札場跡、左手向こうが本陣跡。
「本陣跡」
左手広場になった所が塩尻宿本陣跡。明治の2度の大火で宿のほとんどが焼けてしまい小野家住宅以外これといったものは残っていない。

「脇本陣跡」
左手に中山道、塩尻宿の碑と塩尻宿脇本陣跡の標石。
「陣屋跡の武井酒造」
左手に塩尻宿陣屋跡の標石とその奥に武井酒造。連子格子の旅籠建築で宿場の雰囲気。

「中山道鉤の手跡」
ここが京方桝形、歩道橋の手前右へと曲がる。中山道鉤の手跡の標石が立っている。
塩尻から洗馬へ
「阿礼神社」
右手に式内大宮阿礼神社。大門村の産土神。宿場の守護と災害時の避難所を兼ねた。門前で左にカーブ、小学校の前を通って堀ノ内の集落に入る。
「堀内医院」
右手に旧家、堀内医院とある。
「重要文化財堀内家住宅」
医院の続きに立派な冠木門。前に『重要文化財堀内家住宅』の標柱。

「屋敷」
松本地方独特の本格的な本棟造り。
「大小屋信号の石碑群」
大小屋信号で国道と合流。角に庚申、道祖神、秋葉大神などが並んでいる。
「大門神社」
田川に架かる塩尻橋を渡ると直ぐ下大門交差点。右へ行くと松本街道。ここで左、平出遺跡方面へ進む。この辺りは市街地。右に大門神社、昔は柴宮八幡宮と言った。

「耳塚」
耳の病が治ると信じられているが、桔梗が原の合戦とか安曇族に関係があるとか。
「平出の一里塚」
中央本線のガードをくぐり、右手昭和電工の長い長いコンクリート塀に沿って歩く。塀が途切れた先左手に松の木が見える、これが平出の一里塚。向こうから来る人は同類の街道歩き。木曽から来る人は必ず桧笠を被っている。畑には長芋が植えられている。
「平出の一里塚」
片方の塚しか残っていないが初期の姿を伝える貴重なもの。松は平出の乳松と言われ服用すると乳の出が良くなると信じられている。この松は3代目。

「平出遺跡」
左手に平出遺跡。日本3大遺跡に数えられる古代住居跡。国の史跡に指定され、近くに平出遺跡博物館がある。周りはブドウ畑と長芋畑。中央本線の踏切を渡り、右手農業試験場の前を通り、中山道一里塚信号で国道と交差する。左に曲がって国道を行く。ここでやっと食堂を見付け、昼食をとる。12時45分。
「肘懸松」
平出歴史公園信号で国道から右へ分かれ、しばらくして右に小さな松と碑。肘懸松の標柱。細川幽斎が旅の途中にこの松に肘を懸けて月を眺めたと言う伝説がある。
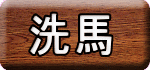
中山道第三十一宿 洗馬宿
所在地 長野県塩尻市
最寄駅 JR中央本線洗馬駅
本陣1、脇本陣1、旅籠29、総人口661、家数163
本山へ 30町(3.3㎞)
「善光寺道追分」
右から北国脇往還、善光寺西街道が合流する。その追分が善光寺道追分。
「追分の道標」
角に道標と道祖神が立つ。正面に『右中山道』、左に『左北国往還、善光寺道』とある。

「洗馬宿の街並」
通りは宿場らしい雰囲気があるが、昭和7年の火災で宿のほとんどが焼失してしまった。
「本陣百瀬家跡」
屋敷は火事で失い、庭のほとんどが洗馬駅に取られてしまった。

「脇本陣兼問屋志村家跡」
生垣の内側に『明治天皇行在所』の碑が立っているのでそれと判る。
「洗馬宿の民家」
宿の名残を残している。
「洗馬宿の碑」
昔は宿の出口、木戸の外に真福寺と言う寺が有ったが、今は公園になっていて洗馬宿の碑が立っている。
洗馬から本山へ
「滝神社の鳥居」
宿を出て坂を下り、左に曲がって中央本線の線路をくぐる。左手小沢川辺に滝神社。
「牧野の一里塚跡」
線路に平行して坂を上ると左手に牧野一里塚之跡の標柱。京へ72里、江戸へ60里。


中山道第三十二宿 本山宿
所在地 長野県塩尻市
最寄駅 JR中央本線日出塩駅
本陣1、脇本陣1、旅籠34、総人口592、家数117
贄川へ 2里(7.9㎞)
「中山道本山宿の標柱と石神・石仏群」
牧野の集落を過ぎ、国道と牧野原信号交差点で合流し、左手浄水場の先で今度は右へ分かれる。左手に『中山道本山宿しののめのみち』の標柱と多くの石神、石仏が並んでいる。
「池生神社入口とそばの里」
右手に『市天然記念物池生神社社叢入口』の大きな看板。この当たりが昔の木戸跡。今はそば切り発祥の地として本山そばの里がある。
「民家・俵屋」
宿に入って左手早速目に入ったのが俵屋の屋号を掲げた大きな民家。なかなか立派なもの。
「旅籠川口家」
右手に川口屋の看板が下がった元旅籠。この並びは旅籠が並んでいた所で、宿場の姿をそのまま残している。
「旅籠川口家の二階部分」
平入出桁造り、二階の格子が見事。

「旅籠屋跡」
池田屋と川口家を振り返ってみる。ガラス戸が外され、自動車が停まっていなかったら、旅人や飯盛女が今にも出てきそう。
「本陣小林家跡」
左手『明治天皇本山行在所跡』の碑が立っている所が本陣と下問屋を兼ねた小林家跡。

「中山道、本山宿碑」
左手に『中山道』の標石と『本山宿』の碑など。
「脇本陣兼問屋花村屋跡」
この場所が脇本陣と上問屋を兼ねた花村屋跡。碑の側に有るのが七変化もみじ、今が紅葉の盛り。

「民家下扇子家」
左手、下扇子屋の屋号がかかった家。障子と壁の白さがひときわ目立ち素晴らしい建築美。

「本山の民家」
宿場の民家の姿を良く残している。
「本山宿の家並」
宿の出口付近から振り返って見る。時計がそのまま止まってしまいそう。
「本山宿の木戸跡」
宿の西の外れ、この辺りに松本藩が置いた口留番所があり、穀物の出入り等を取り締まっていた。そしてこの木戸を出ると、木曽十一宿への旅路となる。
本山から贄川へ
「宿を出て国道19号線に合流」
宿を出て国道に合流、関沢を渡る。左手の山の紅葉が夕日に映えて美しい。釜之沢で国道から右に分かれ歩行者専用道路を行き、狭い踏み切りで中央本線を渡る。
「本山の一里塚跡」
やがて国道から分かれてきた旧国道に合流。その左手に竹垣で囲まれた一里塚跡の白い標柱。これが本山の一里塚跡。この先が間の宿日出塩の集落。

「本山の一里塚跡」
標柱には、「一里塚跡、六十一里塚、江戸より六十一里、京へ七十一里、両側に榎を植えた」とある。
「JR日出塩駅入口」
今回のゴール地点の日出塩駅。
今回の行程は本山宿まで。しかし本山には駅が無いのでその先の日出塩まで足を伸ばす。塩尻峠の上では少し雲がかかって遠望がきかず残念ではあったが、その他はまずまずのお天気で紅葉も素晴らしく、三日間雨に降られずに歩く事が出来たのは、本当にラッキーだったと感謝、感謝。
予定よりはかどり日出塩へ15時10分に到着する。これならひょっとして一本前の『しなの』に乗れるかもしれないと淡い期待を持って駅に入ったら、ガーン! 何とここは無人駅。駅に掲げられた時刻表を見たら、な、な、何と15時代には列車は1本も無く、次は予定していた16時08分の松本行き。今から贄川まで歩くには無理なので、それまで待つしかない。そこへ同類の街道歩きさんがやって来た。八王子から来た人で彼は仕方なくスケッチを始めた。
16時08分松本行きで一旦塩尻まで戻り、16時45分の中央本線特急『ワイドビューしなの26号』で名古屋へ、18時50分の特別快速で豊橋へ、19時50分のJRバス、20時20分無事帰宅。
このウォーキングに出ている間も、アメリカのアフガン空爆は続き、炭疽菌事件の解決の目処はたたず、日本では緊急援助法が国会で成立し、自衛隊の派遣の準備が進められている。世界や日本は何処へ向かって進んで行くのだろうか。
40,190歩
下諏訪~本山 21.8㎞
ページ公開 平成15年1月28日
ページ改良 平成22年11月4日
写真追加 平成22年11月15日
表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ
|































