|
中山道ウォーク その3 平成13年8月27日(月) 松井田から坂本、軽井沢、沓掛まで 初日 8月26日(日) 8月25日(土) 今回も23時30分発、JR夜行バス東京行「伊良湖ライナー」に乗る。22時45分、家内にJR二川駅まで送ってもらう。23時01分豊橋行の電車が時間になっても来ない。駅は既に無人状態で何の情報も入らなし、バスに間に合うのかハラハラドキドキ、いらいらがつのる。23時20分に19分遅れでやっと来た。ギリギリで何とかバスに間に合った。踏切事故の為とか、後もう5分遅れていたらバスに置いて行かれるところだった。 日付が変わって8月26日(日)5時30分東京駅八重洲口に到着。5時45分東京発の京浜東北線で上野へ。6時04分上野発の高崎線で倉賀野まで。7時42分倉賀野着。小さな駅、正面の道を5分ばかり行くと中山道に突き当たる。ここが今日の出発地点。天気は曇り、上空に寒気が入って大気の状態が不安定。所により激しい雷雨が有るかもとの予報。 今朝の新聞のトップ記事は『大地震被害半減へ文科省5年計画』 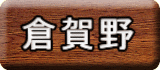 中山道第十二宿 倉賀野宿 所在地 群馬県高崎市倉賀野 最寄駅 JR高崎線倉賀野駅 本陣1、脇本陣2、旅籠32、総人口2,032、家数297 高崎へ 1里19町(6.0㎞) 「須賀喜太郎脇本陣跡」 駅入口交差点、前回はここで終了した。今回はここからスタート。午前7時50分。交差点のすぐ先右手、門構えに白壁、連子格子の二階建が須賀喜太郎脇本陣跡。門は当時のもの、建物は明治23年の再建。明治になっても旅籠屋をしていたと言う。 「須賀喜太郎脇本陣跡碑と景観賞の碑」 門の左脇に脇本陣跡碑と景観賞の碑がある。  「高札場跡」 左隣の須賀医院前は高札場跡。復元された高札と解説板が立っている。  「須賀庄兵衛脇本陣跡碑」 左手に須賀庄兵衛脇本陣跡。建物は無く石塀の前に石碑が立っている。 「倉賀野宿中心部」 脇本陣から宿の中心部を望む。午前8時、日曜日の朝と言うことでまだ人通りが無い。  「倉賀野神社入口」 左手に総鎮守倉賀野神社の石柱と赤い柱に注連縄。ここが神社の入口。 「安楽寺」 右手に安楽寺。ここには天平時代のものと言われる県指定文化財の板碑2基と安永4年(1775)の庚申塔がある。ここを出た所が上の木戸、倉賀野宿の出口である。 倉賀野から高崎へ 「浅間山古墳」 宿を出てしばらく行くと左が開け畑地となり、その先にこんもりとした茂みが見える。これが浅間山古墳。この先広い県道を次の高崎宿を目指して歩く。和田多中町交差点で国道をくぐり、次の交差点を左に行くのが佐野道で、その先に佐野の渡し跡がある。直進して新幹線をくぐり、上信電鉄を渡る。この辺りは高崎の市街地である。   中山道第十三宿 高崎宿 所在地 群馬県高崎市連雀町 最寄駅 JR高崎線高崎駅 本陣0、脇本陣0、旅籠15、総人口3,235、家数837 板鼻へ 1里30町(7.2㎞) 「諏訪神社」 新町交差点を渡った左、街道からは建物の影で見付けにくい所に小さな諏訪神社。お城のような屋根に土蔵造りのミニチュア。火災から社を守るためにこの様な造りになったとか。龍が巻きついた鳥居がお社に張り付いている。  「高崎宿中心部」 高崎は中山道で最も繁華な宿場であったが、城下町のため、本陣、脇本陣共に無く旅籠も少なかった。朝食を取ろうと食堂を探すがまだ開いている所が無い。 「連雀町の朝市」 連雀町では路上で骨董の朝市が行なわれていた。この様なところは宿場の名残かなと思う。  「本町3丁目交差点」 宿はここで左に曲がる。交差点を直進してすぐ右に行くのが前橋道。 「黒壁の蔵屋敷」 左折してすぐ左に黒壁の蔵屋敷。その重厚な建物に時代を感じさせる。 「赤坂町の下り坂」 次の大きな交差点を右に行くのが三国街道。直進すると道幅が狭くなり下り坂、職人の家が目立つ。ここが赤坂町で宿の終わり。  高崎から板鼻へ 「常盤町の民家」 常盤町で右折、左手に格子造りの家。歌川町、並榎町を経て烏川へ。 「烏川の君が代橋」 烏川の君が代橋を渡る。 「烏川の君が代橋」 昔は仮橋で、旅人は橋番に3文を払って渡ったと言う。今は立派な橋。 「国道18号と分かれ右へ」 君が代橋西交差点で国道18号から分かれ右へ、国道406号線を行く。朝食のための食堂探しは諦めて、最寄のコンビニでサンドイッチとカフェオーレで我慢。この後次の二又を右に行く所を誤って左に進む。 「高崎名物のだるま作り」 下豊岡町の道沿いに高崎名物福だるまを作っているお宅があった。日なたに乾された達磨の赤がとっても印象的だった。  「茶屋本陣飯野家」 地図にある高圧線をくぐっても茶屋本陣が無いので道の誤りに気付く。これは大変と取って返し旧道に戻る。左手土蔵に門構えの立派な屋敷、豊岡の立場茶屋本陣、県の史跡に指定された飯野家がある。  「石の仏たち」 茶屋本陣飯野家の向かいに石仏がある。 「藤塚の一里塚」 国道と合流し広い道になる。左手は碓氷川の土手。やがて道の左に榎の大木。これが藤野の一里塚。江戸から28里目。  「藤塚の一里塚」 国道の右手にも木は植わっていないが塚が残っており、塚の上に浅間の祠がある。 「達磨寺」 左手、碓氷川の向こう岸に小さく屋根が見えるのが達磨寺で知られた少林山達磨寺。元禄年間碓氷川中から発見された香木を、行者一了居士が信心、達磨大師坐像を彫刻して草堂に祀ったのが起こりとか。正月七草の福だるま市は有名。 「碓氷川左岸を行く」 碓氷川の左岸を行く。右手前方は八幡町。 の宿。 「八幡宮の大鳥居」 右手に町名の起こりとなった八幡八幡宮(やわたはちまんぐう)の赤い大鳥居が見える。『八幡太郎、奥州下向の時、此所に一宿在りし旧跡』八幡太郎義家奉納の甲冑があり、武将の尊敬が厚かったとか。  「かねつ橋供養塔」 安中市に入り、板鼻東交差点の先右手にかねつ橋の供養塔。石碑と解説の嵌め込まれた石とがある。板鼻宿本陣木島七郎左衛門がここの石橋の改修をした経緯が記されている。 「道祖神」 間も無く道は二手に分かれ国道は右に、旧道は左に進む。すぐ左手に道祖神。 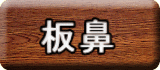 中山道第十四宿 板鼻宿 所在地 群馬県安中市板鼻 最寄駅 JR信越本線安中駅 本陣1、脇本陣1、旅籠54、総人口1,422、家数312 安中へ 30町(3.3㎞) 「榛名・草津道の道標」 JR信越本線の踏切を渡ってすぐの交差点が板鼻2丁目。右に入る道が榛名道で角に道標が立つ。正面に『やはたみち』左に『はるな、くさつ、いかほ・・・』文政13年(1830)の建立。  「板鼻宿の信号」 板鼻宿交差点、この正面が宿の中心部。交差点手前に福田脇本陣跡が有るはず。 「板鼻宿本陣跡標柱」 交差点の先右手、板鼻公民館の前に板鼻宿本陣跡の古びた木柱。ここが問屋も勤めた木島本陣跡。かつての建坪は167坪で門構えと玄関を備えていた。建物は昭和10年代まで残っていたとか。  「皇女和宮資料館」 公民館の裏に、皇女和宮が泊まった木島本陣の書院が保存され資料館として公開されている。 「てうちん屋」 右手に土蔵造りの花屋さん。江戸末期の建築。  「十一屋」 元酒造店で、昔は牛宿と言い移動牛馬の泊まる宿であった。  「板鼻宿西の外れ」 道は細り碓氷川に架かる鷹之巣橋へと続く。 板鼻から安中へ 「鷹巣神社の標柱」 街道の右手、橋の手前に鷹巣神社の標柱。右に鷹之巣山があり、山上には鷹巣城別名板鼻城址や鷹巣神社がある。 「碓氷川の鷹之巣橋」 碓氷川を鷹之巣橋で渡る。昔はこの上流50mのところに渡しが有った。碓氷川の向こう、山上に見えるのが安中の精錬所。 「中宿の民家」 鷹之巣橋を渡り中宿信号で右折、昔の渡し場から来た旧道に突き当たるので左折し旧道に入る。右手中宿の家並みの中にも古い民家が目に付く。 「庚申塔」 横町の左角に庚申塔。ここから左に入る道が昔の一宮・大日街道で、庚申塔の側面に従是一宮大日街道とあり道標を兼ねる。  「道祖神と蚕養神」 街道は碓氷川に突き当たる。昔はこのまま川を渡ったが、今は左に折れ国道の久芳橋で向かいへ渡る。橋へと左に曲がる所に道祖神と蚕養神、この神様は蚕の難しい書体で書かれている。この辺り昔は養蚕が盛んであったことが判る。 「不動尊」 道祖神のすぐそばに不動尊。久芳橋のすぐ近くに牛丼屋を見付け、昼食にする。これは所が変わっても同じ味、同じ値段。 「JR安中駅と東邦亜鉛安中精錬所」 駅前歩道橋から見る安中駅。その向こうは山の斜面全体が東邦亜鉛安中精錬所、まるで蜂の巣砦の様。  「碓氷川の久芳橋を渡る」 橋を渡り下の尻交差点で国道と別れ左に入る。  中山道第十五宿 安中宿 所在地 群馬県安中市安中 最寄駅 JR信越本線安中駅 本陣1、脇本陣2、旅籠17、総人口348、家数64 松井田へ 2里16町(9.6㎞) 「安中宿下の木戸跡」 国道と分かれ安中の町に入って間も無く右手に、安中宿下の木戸跡の標識がある。ここから安中宿に入る。  「熊野神社参道」 右手に熊野神社参道。脇に『非戦の先覚者柏木義円の墓入口』の標識がある。 「貫禄の有る旧家」 宿の左手に大きな民家がある。どのような仕事をしていた家なのだろうかと想像を巡らす。 「安中宿中心部」 左手にある郵便局の所が本陣跡。 「安中宿本陣跡」 左手、郵便局の前の駐車場脇植込みに本陣跡の碑と標識がある。  「大泉寺」 本陣跡の向かい、少し奥に入ったところに浄土宗の寺大泉寺。門前に大きな庚申塔がある。 「旧碓氷郡役所」 伝馬町交差点を右折、街道からそれ、坂を登った突き当りが旧碓氷郡役所。この辺り一帯が安中城址。明治45年に建てられたもので、郡役所として現存する群馬県内唯一のもの。 「大名小路」 郡役所前を左折した通りが大名小路。 「郡奉行役宅」 大名小路に復元された郡奉行役宅。  「足軽長屋」 大名小路に復元された足軽長屋。  「黒壁蔵造りの薬屋さん」 宿の通りに戻って右手に黒壁土蔵造りの薬屋さんがある。落着いた良い雰囲気。 「新島襄先生旧宅入口標識」 町並みの終わり近く、左へ入る道の角に『新島襄先生旧宅入口』の標識。新島襄は熱烈なキリスト教の伝道者で京都の同志社大学の創始者でもある。安中藩士の家に生まれた。 「新島襄先生舊邸宅入口の石柱」 この辺りで安中宿を出る。 安中から松井田へ 「天然記念物安中原市ノ杉並木碑」 宿を出て間も無く右手に大きな杉並木の石碑がある。昔は立派な杉並木が6里も続いたと言われ、昭和8年に天然記念物に指定された。しかしいろんな理由で少しずつ減り、国道と交差するところまでのものは、昭和43年に全て伐採され碑だけが残った。 「杉並木」 安中実業高校前で国道と交差し、原市に入ると並木が残っている。この辺りの地名が一里山。 「若い杉が植えられている」 若い杉が植えられて、復元の努力がされている。 「原市高札場跡、明治天皇原市御小休所碑」 杉並木が終わり、原市3丁目の左手に原市高札場跡の標識と明治天皇原市御小休所の大きな石碑が立っている。ここが茶屋本陣の跡。  「地蔵堂」 右手の原市小学校と安中市立二中を過ぎ八本木に入ると、石段の上に地蔵堂。安中市指定重要文化財地蔵菩薩像の看板がある。 「八本木の旧立場茶屋山田屋」 左手、地蔵堂の向かいに旧家、八本木立場茶屋跡の標識がある。白壁と連子格子が美しい。ここが旧立場茶屋山田屋。  「日枝神社」 磯部温泉への道を横切り郷原に入る。右手に日枝神社。真新しい石の鳥居とその奥に社叢がある。 「自性寺」 日枝神社の先右手に自性寺、新島襄先生先祖菩提寺とある。 「郷原の高札場跡」 左手、住宅の生垣の向こう、釣瓶井戸の隣に高札場跡の標識。 「郷原の妙義道常夜灯」 国道が左から合流した交差点の左手に、大きな常夜燈と幾つかの石碑、標識、解説板がある。これが文化5年(1808)建立、台座に妙義道と彫られ、道標を兼ねた常夜燈である。ここからの道は今、通行不能となっている。 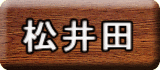 中山道第十六宿 松井田宿 所在地 群馬県碓氷郡松井田町 最寄駅 JR信越本線松井田駅 本陣2、脇本陣2、旅籠14、総人口1,009、家数252 坂本へ 2里15町7間(9.5㎞) 「松井田宿下の木戸跡」 しばらく国道を行き、やがてバイパスが右に分かれ街道は左を進む。市街地入口信号の辺りが江戸口と呼ばれた下の木戸跡。ここからが松井田の宿。 「妙義山登山口の看板を掲げる店」 左へ曲がる道が妙義道。角には、二階の張り出した袖壁に『妙義登山口』と道案内を書いた民家がある。 「伝衛門脇本陣跡」 道の反対側、宿の右手に伝衛門脇本陣跡。  「外郎陳道斎の店跡」 宿の右手、山城屋酒店辺りが外郎陳道斎の店跡。東海道小田原で今も続いている『ういろう』の分家が有った所。 「金井本陣跡」 宿の左手、群馬県信用組合の横から裏に回った、仲町公民館辺りが金井本陣跡と言われている。 「仲町の立派な民家」 中町信号右先角の立派な民家、どのような商いをしていたのか。右へ入る道が榛名道。 「辻中薬局」 宿の左にある薬局、街道時代からの看板を店内に飾っている。 「上町の民家」 上町の右手、この並びに松本本陣跡が有るのだが、場所がどこだったのか特定出来ない。  「松井田宿上の木戸跡」 上町の外れ、小学校への歩道橋が架かっている辺りが上の木戸跡。松井田宿の西の出口にあたる。ここには高札場が有って、右へ入ると松井田八幡宮。 松井田から坂本へ 「新町の民家」 宿を出てしばらくは街道沿いに民家が続く。中には出桁造りの家があり昔の名残が感じられる。 初日は西松井田駅入口交差点までとし、16時15分で打ち上げる。松井田宿に入って少し雨がぱらついたが大した事無く、予定どおり歩く事が出来た。16時25分の信越本線高崎行きで高崎まで戻る。予約しておいた駅前のビジネスホテルに入る。夜は駅ターミナルビルの店で食事と一杯。隣の席のお客さんと意気投合、互いの趣味の話で盛り上がる。店のおやじが良い話を聞かせて貰ったと言ってサービスしてくれる。 50,317歩 倉賀野~松井田 26.1㎞ ページ公開 平成14年12月10日 表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |