|
中山道ウォーク その5 平成13年10月31日(水) 和田 平成13年11月 1日(木) 和田から下諏訪まで 平成13年11月 2日(金) 下諏訪から塩尻、洗馬、本山まで 初日 10月31日(水) 前夜寝床に入るまで、今回の和田宿への行程は、東海道新幹線経由、長野新幹線上田までのルートを考えていた。しかし、今朝寝床でふと思い付いた。ひょっとして名古屋、篠ノ井経由でも時間的に間に合うのではないかと。朝起きて一番に時刻表を見ると出発時刻を早めればOK。朝食を抜きにして急いで家を出る。これで約6,000円のお得。7時10分のJRバスで豊橋駅へ、7時45分の特別快速で名古屋へ、9時00分の中央線特急ワイドビューしなの7号で篠ノ井まで、11時49分のしなの鉄道で上田まで、12時40分のJRバス上和田行きに無事連絡。13時45分上和田へ到着。 今回の中山道ウォークは日本橋から順に歩いているため、どうしてもその道順で考えてしまい、名古屋、篠ノ井経由がぎりぎりまで思い付かなかった。頭が固い。あぶない、あぶない。今日は快晴、気分爽快。名古屋駅のホームで朝食を取り乗車、木曽路は今紅葉、黄葉の真っ盛りで見事な景色。上和田到着後、役場前のお店で昼食。先月に来た事を覚えていてくれて、街道歩きの話が盛り上がる。 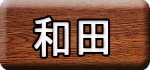 中山道第二十八宿 和田宿 所在地 長野県小県郡和田村 最寄駅 長野新幹線・しなの鉄道上田駅 本陣1、脇本陣2、旅籠28、総人口522、家数126 下諏訪へ 5里18町(21.6㎞) 「黒曜石石器資料館」 旧石器時代には和田峠は日本有数の黒曜石の産地で、ここの石が全国の遺跡から出土する。この資料館には男女倉遺跡からの出土品が展示されている。 「信定寺」 武田信玄が和田城を攻め、城主和田信定公の菩提の為に建てられた。和尚さんが出てきていろいろな寺宝を見せてくれた。  「高札場跡」 上町の右手に高札場の跡、解説板が立てられている。 「西の木戸跡からの眺め」 上町と鍛冶足との境辺りが西の木戸跡。バス停から山を見ると西日で輝いていた。  上和田へ入るのに上田からのバスが、朝晩2便しかない為どうしても中途半端。今日はとにかくこの宿へ入るだけ。峠への挑戦は明日にして、先回見学する時間がなかった黒曜石石器資料館、歴史の道資料館かわちや、和田宿本陣をゆっくりと見学する。最高に良い天気、周囲の山々の黄葉が素晴らしい。午後4時に今日の泊まりの旅館本亭に入る。江戸末期の建物そのままの旅館。二階の部屋に案内され直ぐに石油ストーブに火が入れられる。熱い沸きたての風呂に入って、午後6時に夕食、ここでも朝鮮人参の天婦羅が出た。望月でもそうだった。この辺りの名産か。もう一人同年輩の街道歩きの人が泊まっている。街道歩きの話を肴に酒を酌み交わす。 10,238歩 和田宿 二日目 11月1日(木) 6時起床、お天気は昨日程ではないが悪くもなさそう。とにかく寒い。ここのトイレはボットンのメシャコ、これには参った。7時から朝食、昨夜は気が付かなかったが、一階の食事の広間には槍や提灯、高札が掲げられ、襖絵はとある画家の芭蕉とその門人の絵。それぞれがお宝みたい。お弁当にとおにぎりを作って貰って、7時45分出発。本亭の前で奥さんに記念写真のシャッターを押してもらう。 「本亭の座敷の槍や提灯」 食事をした部屋の壁や鴨居には槍、御用の高張提灯、笠などが掛かっている。  「本亭の座敷の高札」 もう一方の壁には高札が2枚、何れも正徳元年(1711)のもの。 「本亭の座敷の襖絵」 とある画家がこの旅籠に泊まって、描いた芭蕉とその門人の襖絵。  「本亭前にて」 朝、出発を前に記念写真。  和田から下諏訪へ 「和田の一里塚跡」 鍛冶足の集落を過ぎ国道142号と交差する鍛冶足信号交差点に中山道一里塚跡の碑。江戸から50里目。  「牛宿」 大出集落を通り日向で国道に合流、しばらく国道を行く。途中で側溝に大きな鹿が死んでいるのを見る。夜中にトラックにでも跳ねられたのか? かわいそうで写真には撮れない。間も無く牛宿バス停、名前のとおり牛宿があったところ。 「扉峠入口」 美ヶ原の扉峠への分かれ道。 「唐沢の立場跡」 旧一の橋を渡り唐沢の集落に入る。ここは立場茶屋が有った所で、右が旧茶屋本陣羽田家。 「唐沢の一里塚」 唐沢を出て国道と合流。直ぐ先左手に中山道唐沢一里塚跡の標石と階段がある。上からは唐松の落ち葉が雨の様に落ちてくる。日に輝いてダイヤモンドダストのよう。 「一里塚」 街道の位置が変わったため、丘の上に塚がそのまま残された。江戸から51里目。  「男女倉バス停」 左は新和田トンネルへの有料道路、右が旧国道。ここで峠から下ってきた夫婦に出会う。 「観音沢から山に入る」 街道は右の旧国道から左へ分かれ『歴史の道』の標識に従って山に入る。  「休み茶屋跡」 枯葉を踏んで進むと右手に休み茶屋跡。 「三十三体観音」 休み茶屋跡の直ぐ上に三十三体観音。熊野権現社の前に有ったものを調査発掘して集められた。千手観音、如意輪観音、馬頭観音などがある。熊笹が刈られ落ち葉してとても歩き易い。 「接待茶屋跡」 観音坂を上りきり国道に合流した所に昭和58年に復元された通称接待茶屋。国史跡永代人馬施行所。江戸呉服町の豪商かねや与兵衛が幕府へ金1000両を寄付して碓氷峠と和田峠に作った。11月から3月まで峠を越える旅人に粥と焚き火を、牛馬には桶一杯の煮麦を与えた。文政11年(1828)から明治3年(1870)まで続けられた。  「石灯篭」 国道は右に急カーブする。その左手を石灯籠に向け再び山に入る。 「避難小屋」 樹林帯、湿地帯の長坂を上る。間も無く避難小屋。 「石畳」 避難小屋を過ぎ、新長坂で石畳が現れる。 「石畳道」 少しの間石畳道。箱根には及ばないが時代を感じさせる。 「広原(東餅家)の一里塚跡」 急坂を上りきると視界が広がり平らな所に出る。ここに広原の一里塚。この辺り冬は雪で難渋する所。片方の塚が残っている。江戸から52里目。  「東餅家の立場跡」 左手のキャンプ場の脇を通り国道に出る。大きくカーブしたところが東餅家の立場跡。ドライブインがある。 「東餅家の解説板」 右の道路脇に東餅家の解説板。昔は5軒の茶屋が名物の力餅を売っていた。幕末には茶屋本陣も有ったと言う。 「ビーナスラインの料金所」 東餅屋から国道とビーナスラインを5回横断し、和田峠スキー場の薄野原の右端を真っ直ぐに上ると峠につく。 「御岳遥拝所」 峠に辿り着いた旅人はここから御嶽山を拝んだ。 「和田峠」 後には浅間山、前には御嶽山や木曽駒ヶ岳が望めるところ。標高は1,600m、分水嶺。  「賽の河原と地蔵」 ガラガラとした石の上に地蔵菩薩坐像。 「古峠の解説板」 ここを諸大名の参勤交代行列や一般の旅人達、荷物を運ぶ牛馬が通って行った。 「和田峠」 向こうは上ってきた道、東坂で和田から2里21町(10.15㎞)『やすらか』と言われた。ここを3時間30分、17,943歩で上がってきた。これから先の西坂は下諏訪まで2里27町(10.8㎞)『けわし』と言われた。  「下りのガレ場」 峠で小休止と放尿の後、下りに入る。急斜面をジグザグや左に右に横断しながらの下り。カメラは一時片付けてザックに入れ、両手を使えるようにして慎重に下る。道は悪いが『歴史の道』の白い道標が要所に立てられているのでルートを探す心配は無い。 「水飲み場」 急な下り坂の途中にある。苔むしている。 「熊笹の中を下る」 峠沢の右岸を下る。 「石小屋跡」 風雨を避ける避難所として設けられた小屋の跡。  「大曲小曲の唐松林」 唐松林、下は熊笹の道。唐松の落ち葉は絨毯の上を歩く様で快適。 「唐松の黄葉」 急に視界が広がり正面の山の唐松の黄葉が見事で、しばし見惚れる。 「国道を横断する」 国道に出会いこれを横断する。 「紅、黄、緑」 紅葉と黄葉と褐色葉そして緑の葉が入り混じり日に映えてとっても綺麗。  「山ノ神の側の大きな倒木」 国道が下に見えた所の右手に山の神の小祠。そのそばに大きな倒木が2本、山の神に守ってもらえなかったのか? ここで小休止。旅館で作ってもらったおにぎりで昼食とする。 「牛頭天王」 2度目の国道の横断をし、再び草叢を分け入ると右手に牛頭天王碑と道祖神。 「西餅屋立場跡」 国道に出る直ぐ脇に広場があり西餅屋茶屋本陣の碑と解説板。ここが西餅家の立場跡。 「西餅屋の一里塚」 3度目の国道を横断し、ガードレールを越え雑木林の中に入る。ここからは案内標識無くルートが判り難く不安になる。程無く一里塚碑が有ってほっとする。江戸から53番目。その後垂木坂のガレ場を横断する。とんでもない道。  「国道を歩く」 笹薮をこきながら下ると国道脇に出る。左に迂回して林道から国道に出る。両脇の紅葉が素晴らしい。行き交うトラックに気を付けさえすれば、快適な下り。 「浪人塚入口」 国道の浪人塚入口標識から左に入り国道をくぐると浪人塚の解説板。 「浪人塚」 中央の塚が水戸浪士を葬った塚。紅葉が美しい。  「樋橋」 浪人塚を過ぎ樋橋の立場へ向かう道は黄葉がとっても綺麗。 「山の神」 左手に山の神。 「樋橋立場跡」 国道と合流した所、左手に樋橋茶屋本陣の碑と解説板。落ち葉を敷き詰めた中に有る。 「中山道樋橋宿本陣延命地蔵大菩薩 茶屋本陣跡の向かいに地蔵堂。本によっては観音堂だったり、薬師堂だったりする。 「深沢」 深沢の集落に入る手前で、突然ギィーと言う鳴声と共に雉が2羽目の前に着地する。驚いて一瞬足がすくむ。冷静に戻ってカメラを向けようとした次の瞬間、再びギィーの鳴声と共に飛び去る。一瞬の出来事ではあったが感動で胸がワクワクする。右手砥川の向こうの山がとっても綺麗。自然が一杯残っている事を実感する。 「一里塚跡」 国道から右にそれ産廃処理会社の横から裏へ回ると一里塚の碑と解説板が立っている。江戸から54番目。  「町屋敷団地の道祖神」 国道へ戻って町屋敷バス停から今度は左の住宅地に入る。公会所前に道祖神が有り、これには4本の御柱が立っている。 「天下の木落し坂の碑」 その先へ進むと数本の松の木の脇に大きな石碑と解説板。碑には『諏訪大社下社御柱街道天下の木落し坂』とある。ここが坂の上にあたる。 「木落し坂の御柱」 坂の上には、この坂を訪れた人が木落しの豪壮さを想像し、臨場感に浸れる様観光用の御柱が奉納されている。この大木は樅の木で樹齢は200年。  「木落し坂」 木落し坂を横から眺めるとその凄さがわかる。  「芭蕉句碑」 国道落合橋までコンクリートの遊歩道で降りてくる。降りた所に芭蕉句碑と道祖神がある。このあと注連掛バス停を過ぎ初めて前方に諏訪湖が見える。 「道祖神」 砥川発電所の送水管を左に見て、右の住宅地に入る。ここの道祖神にも御柱が立っている。  「諏訪大社春宮の杉並木」 国道に戻りしばらく行くと『諏訪大社下社春宮』の大きな看板があり、これに沿って右に行くと春宮の杉並木となり右手下方に社が見える。 「諏訪大社春宮」 杉並木の途中から下に下りると春宮の右横へ出る。参拝をする。これが2度目。 「万治の石仏」 春宮の左から砥川を渡ると畑の中に万治3年(1660)に刻まれた大きな石仏。  「諏訪大社春宮正面」 春宮の正面に回ってもとの杉並木に戻る。  「下諏訪の街と諏訪湖」 杉並木の外れで左に曲がる。ここからは下諏訪の町が一望でき湖面の光るのが見える。右へ行く塩尻道と分かれ直進する。 「慈雲寺入口・竜の口石碑群」 慈雲寺の階段前に出る。ここは竜の口と呼ばれ、口から水が流れ出している。多くの石碑がある。 「下ノ原の一里塚跡」 なだらかな坂を下ると住宅地になり、右の黒塀を背に一里塚碑。江戸から55里目。  「下ノ原の街並」 このあたり落着いた街道らしい街並。 「御作田社と温泉」 左に御作田社。大社へ供える神田を司るお宮。石垣のパイプからは温泉が出ている。 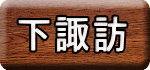 中山道第二十九宿 下諏訪宿 所在地 長野県諏訪郡下諏訪町 最寄駅 JR中央本線下諏訪駅 本陣1、脇本陣1、旅籠40、総人口1,345、家数315 塩尻へ 2里32町(11.4㎞) 「番屋跡」 小さな十字路の角に番屋跡の碑がある。ここからが下諏訪の宿。 「古い街並」 古びた宿場街らしい家が並んでいる。 「旦過の湯と湯田坂」 急な上り坂になる。これが桝形がわりの湯田坂で、左手には『諏訪温泉―下諏訪駅に三所あり』と言われた三つの温泉の中の一つ、旦過の湯がある。  右手には茶屋跡に今井邦子文学館。 「来迎寺」 左手に来迎寺の参道。ここの銕焼地蔵にまつわる和泉式部伝説で有名な寺。 「和泉式部の守り本尊銕焼地蔵尊」 下諏訪の問屋の下女カネが、この地蔵の加護で出世し、宮中に仕え和泉式部となった。 「古い民家」 宿場らしい民家。 「児湯」 下諏訪三湯の一つの児湯。  「旧本陣岩波家」 左手に立派な門構えの本陣跡。岩波家は本陣と問屋を兼ねた宿場を総括する家柄であった。  「屋敷入口」 屋敷の前方部分は失われているが、奥の座敷や庭園、土蔵などに古いものが残されている。 「座敷から庭を見る」 中山道随一の名園と称される自然の地形を利用した築庭式庭園。 「座敷」 洗練された京風数奇屋造り座敷。皇女和宮が泊まり、明治天皇も小休止したと言う。 「最も古い建物、蔵」 この本陣で最も古い建物。 「関札」 誰が宿泊しているかを知らせるのがこの関札で、玄関前に高々と掲げられた。 「問屋場跡」 本陣の隣り、丁字路の突き当たりに問屋場があった。ここを直進すると甲州街道で、宿は右に曲がり旅籠が続く家並を通り、西の枡形を出て京へと向かう。  「茶房まどか」 丁字路の角にある建物。宿場の雰囲気を残す。 「古い民家」 問屋場の直ぐ隣り、甲州街道沿いの家。 「ききょうや」 丁字路で曲がった立町の左手にある創業元禄3年(1690)の老舗旅館。  「下諏訪町歴史民俗資料館」 左手、宿の民家を利用して宿場関係の資料を展示している。 「みなとや」 左手、ここも江戸時代から続く旅館。店先に古い看板が吊り下げられている。 「宿の街並」 資料館、みなとやの並びの街並。 「桝形」 西の桝形。中山道下諏訪宿の提灯が下がっているのが中山道。大きなモニュメントが御柱グランドパーク。ここでも温泉が湧いている。  「高札場跡」 桝形の左手、御柱のモニュメントの陰に隠れるように高札場が復元されている。 「赤い郵便ポストが似合う街」 今夜の宿へ向かう為枡形から引き返す。立町から問屋場方面を見る。宿場の家並に赤い郵便ポストが良く似合う。 「塩羊羹の新鶴本店」 問屋場から秋宮へ向かう左手に、塩羊羹の新鶴本店。 「綿の湯の壁の昔の宿場絵」 問屋場の奥が下諏訪三湯の一つの綿の湯。壁面に宿場の絵が掲げられている。  「問屋場跡碑と綿の湯の解説板」 右の中山道下諏訪宿問屋場趾碑には「甲州街道終点、右江戸へ五十三里十一丁、左江戸より五十五里七丁、正面京都へ七十七里三丁とある。また解説板には綿の湯の神話と伝説が記されている。  「諏訪大社秋宮拝殿と御柱」 秋宮を参拝する。御柱が夕日に照らされている。 「諏訪大社秋宮」 菊花展開最中、秋真っ最中。  「諏訪大社秋宮正面」 秋宮の正面、七五三ご祈祷受付の看板、これも秋の風物。 「ホテル山王閣」 今夜の泊まりホテル山王閣。 和田峠では雲が出て日差しは無かったが、峠を下るにしたがって天気は良くなり、素晴らしい紅葉や黄葉を楽しみながらの街道歩きとなった。上りでは鹿が死んでいたり、下りでは目の前に雉の夫婦が飛び出してきたりで、まだ自然がいっぱい残っている事を知らされる。下諏訪の宿には思いがけず古い姿が沢山残っていて感動する。 午後4時に予約しておいた国民宿舎のホテル山王閣にチェックイン。さっそく温泉に浸かって汗を流す。温泉での泊まりにしたのは正解だった。食事も結構いける。いまどきこんな格安の泊まり方が有るのかと、勉強になった。 40,190歩 和田~下諏訪 21.6㎞ ページ改良 平成22年11月2日 写真追加 平成22年11月14日 表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |