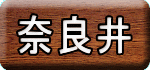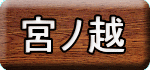|


「二百地蔵」 杉並木の直ぐ上の山の斜面に地蔵堂があり、その前に聖観音、千手観音、如意輪観音はじめ色々な石仏約200体が集められている。これは明治期の国道開削や鉄道敷設のときに奈良井周辺から集められたと言う。 「八幡神社」 これが八幡神社で奈良井義高の館の鬼門除けと言われ、社殿は天正年間に造営されたとある。 「下町を望遠で撮る」 宿に戻って再び下町から上町へと宿場を歩く。200㎜の望遠で撮ってみた。 
「杉の森酒造の酒林」 軒に吊るされた酒林が人目を引く。 「中町の朝、越後屋」 越後屋をはじめ宿の家並の向こうに鳥居峠へと続く山が迫っている。 
「中町の朝、伊勢屋」 この1台の車が停まっていなかったら、何時の時代かわからない。 

「桝形の高札場と水場」 上の桝形には水場と、再現された高札場がある。 
「鎮神社」 宿の外れの右手に鎮座する。奈良井の宿の総鎮守、境内に楢川村歴史民俗資料館や青邨句碑がある。 「青邨句碑」 お六櫛つくる夜なへや月もよく 青邨 「有料駐車場のSL」 鳥居峠にかかる前に、お手洗いを済ませておくべく、左手踏切の先にある有料駐車場へ寄る。そこに懐かしい蒸気機関車C12119が展示保存されていた。

「石畳」 やがて石畳道になる。比較的平たい石が敷き詰められており歩き易い。 
「中の茶屋跡、葬り沢」 周りの木々は新芽が出たところ、足元には小さな花が咲き、小鳥が盛んに囀っている。登りが続くが気持ちが良い。小さな橋を何度か渡り、左上の展望台を過ごすと中の茶屋。天正10年の合戦での屍を葬ったので葬り沢と言う。 
「中利茶屋跡」 急坂を上り詰めると車の通る砂利道に出る。左手にあるのが中利茶屋(峰の茶屋)の跡、今は山小屋風の建物がある。 「鳥居峠」 砂利道を進むと楢川村と木祖村の境界があり、その先で視界が急に開け御岳方面が一望出来る。峠到着9時45分。家内は初めての街道歩きだのに順調、良かった〜。ここが分水嶺、日本列島の背骨に当る。今までの奈良井川は北へ流れ日本海へそそいでいたが、ここからは木曽川となり南へ流れ太平洋へとそそぐ。 

「御嶽遥拝所の鳥居」 右手小高くなった所、石段の上に石の鳥居、ここが御嶽遥拝所。鳥居峠の名前の由来となった鳥居がある。峠の標高1197mはここなのか先の分かれ道の所なのか? 
「御嶽遥拝所」 鳥居から神社までとその周辺に多くの石碑や石仏などがある。こんなに大きな石をどのようにして運び上げたのだろうか。 「遥拝所より御岳を望む」 ここからは雪の残った御嶽が一望出来る。しかし残念ながら頂上には雲がかかっている。 
「御岳手洗水鉢と中山道碑」 鳥居を過ぎると下りになる。遥拝所の下辺りに手洗い水と中山道の碑。この上には義仲の硯水がある。 「丸山公園の碑群」 更に下ると右手に丸山公園。鳥居峠の石碑や二つの芭蕉句碑がある。 木曽の栃うき世の人の土産かな 天宝3年(1843)建立 雲雀よりうえにやすらふ峠かな 享和元年(1801)建立 
「熊除けの鈴」 熊除けの鈴お鳴らし下さいの看板の下に手振りの鈴が置かれている。下から上がって来る人が必ず『熊出ませんでした?』と聞く。用心用心。 
「石畳」 その先に石畳。足を挫かないように慎重に下る。やがて七曲り、登ってきた時より勾配がきつい。視界が開けると舗装道路と交差する。右に消防署、右向かいには公衆トイレと鳥居峠の案内図。振り返ると熊に注意の看板、だから登ってくる人がみんな『熊出ませんでした?』と聞いたのだ。ここまで下って10時30分順調である。 
「天降社」 道路を横切ると住宅になる。しかし道は急勾配。左に白木の鳥居の天降社。そばに天降社の大モミジ。 「尾張藩薮原御鷹匠役所跡」 更に下ると右手、住宅の庭のような所に尾張藩薮原御鷹匠役所跡の白い標柱と解説板。かつて尾張藩が鷹狩用の鷹の捕獲と飼育のために設けていた役所の跡。見晴の良い所で、そばに眺望案内の説明板がある。 
「飛騨街道分岐点(追分)標柱」 その先左の道路脇に飛騨街道分岐点(追分)の標柱。飛騨高山への街道の追分として賑わった所。そして道は中央本線の線路に突き当たる。線路に沿って左折、上の方左に藪原宿の産土神薮原神社と『お六廟』のある極楽寺がある。ガードを右へくぐると薮原の宿である。


「旧旅籠米屋與左衛門」 宿の左手、庵看板の庵だけが下がり、入口に米屋與左衛門の看板。中山道やぶ原旅籠こめや。 

「そばまんじゅうの庵看板」 そばまんじゅうの庵看板が白壁に映えて印象的。 「水場」 左手に水場、源流の里二又水道組合の看板が下がっている。昔からこの水を大切に守り続けて来たのだろう。 
「ぬり櫛處と書かれた櫛型看板」 宿の左手、大きな櫛にぬり櫛處と書かれた看板が下がっているのが宮川漆器店。裏の土蔵を資料館として公開している。 
「お六櫛の店」 その先にお六櫛の問屋篠原商店。お六櫛とは白木のミネバリの木で作った細密なスキ櫛のこと。妻籠宿の旅籠の娘お六は頭痛で悩んでいた。或る時御嶽権現のお告げでミネバリの木で櫛を作り髪をすくと頭痛が治った。以来この櫛をお六櫛と言い妻籠の名物となった。しかし妻籠のミネバリが無くなり、薮原の物を使った。そこで薮原の藤屋が虚無僧姿に変装し妻籠の技術を習得し、名声まで奪ってしまったと言う。その後300年薮原の特産品となっている。 

「薮原宿高札場跡」 宿の外れ右手に赤いレトロな郵便ポスト。そばに句碑と薮原宿高札場跡の標柱が立っている。この辺りで宿を出る。

「山吹トンネル」 薮原を出たらしばらくは国道を行く。左から山、国道、線路、木曽川の順で、国道を行くトラックや自動車は無視し、周りの桜や新緑を楽しみながら歩く。獅子岩橋、鷲鳥橋、を過ぎ吉田洞門。歩道は洞門の外にあり排気ガスから逃れる事が出来た。吉田橋を渡ると今度は山吹トンネル。通り抜けるしか手が無い。トラックが来ると猛烈な音、歩道は設けられているが生きた心地がしない。 
「宮ノ越へ」 トンネルを抜けると神谷橋、左手先には権兵衛茶屋があったと言う。ここから伊那へ向かうのが権兵衛街道と言いここはその分岐点。次の山吹橋を渡ると交差点があり、その先右手に宮ノ越宿の看板。ここを右折して国道と分かれ宿へと向かう。 「句碑」 右手木曽川の向こうが山吹山、トンネルから出てきたJRの線路をくぐると、川を背に句碑。作者の名前は読めない。 豊かなる花の薫りや鳥の聲 「巴ヶ淵」 木曽川に架かる橋が巴橋、その下が巴ヶ淵。橋を渡った右手に義仲手洗いの水。 
「有栖川の宮小休止跡碑」 木曽川を左に見て静かな街道を行く。やがて徳音寺の集落、中程右手に有栖川の宮小休止跡碑。 
「中央アルプスが見える」 左手山の間から中央アルプス木曽駒ケ岳方面が見える。雪を頂いた山を見ると感動する。 「義仲館」 12時30分を過ぎて、そろそろお腹が減ってきた。食堂を探そう。この辺りなら義仲館の近くか駅前か。葵橋を渡らず田の中の道を行き義仲館へ寄ったが周りには何も無い。次は宮ノ越駅へと向かったがお店は一つも無い。では宿場へと勇んだがここにも全く無い。「この辺りの人は外食しないのかしら」 「きっとお金貯めてるね〜」。仕方なく、たった一軒有ったスーパー(何でも屋さん)でのり巻きと大福とお茶を買って、近くの空き地に腰をかけてお昼とする。(この後、原野の駅まで来ても何も無かった) 
 「本陣跡遺構」 
「脇本陣跡」 左手に脇本陣兼問屋場之跡。 「宮ノ越宿民家田中家」 右手に民家田中家。元旅籠であった家を再建したもので宿場民家の典型。 
「田中家解説板」 入口の彫刻や二階出梁の持送りの彫刻は大工の建築水準を表し、棟梁から施主への祝儀とする習わしがあった。 「明治天皇宮ノ越御膳水」 左手に御膳水。江戸末期に掘られた井戸で、本陣で休んだ明治天皇にこの井戸水でたてたお茶を献上した。昭和初期まで近郷随一の名水と言われた。 

「中央アルプス木曽駒ケ岳」 左手の山間から雪の残った中央アルプスが見える。 
「原野の家並」 出梁造りの民家が残る間の宿、原野に着く。
ページ公開 平成15年1月29日 表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |