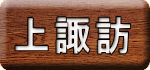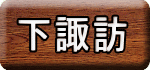|
����ځ@2��4���i���j


 �u���̊X���v �ĂъX���ɖ߂��z�K�ւƌ������B�����痈�������ƍ������㌴�����̌����_���߂���ƁA���̐M�����㌴�����B���̌���ῂ������炢�̗ǂ��V�C�B  �u�㌴�����v �����H�̍����ʁA�̌��E�ƍ��E�̑�ɋ��܂ꂽ�悤�ɒ��A���������������B�������A���H�ɉ����ċ��Ԃ̃t�F���X�����菄�炳��A���ʂɂ͔������邪�����Ă��āA�������������Ă��Q�肷�邱�Ƃ��o���Ȃ��B������ꐡ�������B 
 �u�^�e�O���~�̉Ɓv �Â��X���ɏo�āA�Ăѐz�K�炵�����Ƃ�������悤�ɂȂ��Ă����B�E��̉Ƃ͓T�^�I�ȃ^�e�O���~�ʼn����ɂ͌܊p�`�̐��^�̃X�Y���I�h�����t���Ă���B 

 �u���x���v �E��Βi�̏�A�傫�ȐΒ��̉��ɎR��̂���̂����юR���x���B ����̂��ƁA�����͑����@�̂����ŁA�]�ˎ��㏉���̊��i8�N�i1631�j�A�����ˏ���ˎ�z�K�������J��B�z�K�����͏�Ђ��J���Ă��錚�䖼���_�̒��n�̐z�K���ł���B  �u������̓J���[�̌b����l�v ����ɂ��邨��̑��ɂ́A���x�͑��ނ��Ă���J���[�̌b����l������B�ۂ̒��Ƀf�U�C�����ꗧ�̓I���W�G�̂悤�ł���B���Ă��Ċy�����Ȃ��Ă���B 
 �u�^�e�O���~�̉Ƃ�����Ō��v �E�菬�������Ƀ^�e�O���~�̉Ƃ�2������Ō����Ă���B  �u�Γ������v �_�˂̏W���ɓ���ƉE��ɉΓ��i�ЂƂڂ��j����������B����ɂ��ƁA�䒌�N�̖~�̏\�ܓ��̗[�A���̐�̗��d�@�̗��R�ŁA�����`�ɏ�������ׁA�������Đz�K���_�֕�[�����B���̎R���u�Ƃڂ���v�ƌ����B  �u���d�@�v �E��Q���̉��ɐ^�V���������̑����@�_���R���d�@������B ����ɂ��ƓV��11�N�i1542�j���̂�����ɂ���K����Őz�K���d�͕��c�M���ɔs��b�{�Ŏ��Q�����B��͍b�{�̓������ɂ��邪�A���̒n�ɕ�Ƃ��ė��d�@�����ĕ�⸈�[�߂Ă��̗�����{�����B 

 �u�����ɃX�Y���I�h���ƉG�Ђ��AX���^�X�Y���I�h���̂���Ƃ����ԁv �l�ꏬ�w�Z�����t�߂̍���ɂ���3���̂���ꂼ��X�Y���I�h���̃f�U�C�����Ⴄ�B��O�̉Ƃ͒��Ɋi�q���g�ݍ��܂ꂽ�^�C�v�A���̉Ƃ͐��^�܊p�`�̃^�C�v�A���̉Ƃ͒P���Ȃw���^�B����ׂ��o���Ėʔ����B 

 �u�Ύ��̒��̓��c�_�v �X���̉E��A��ς��K�̒��ɑo�̓��c�_������B��ɐΔ肪�L���������̔肩�͕s���B  �u�o�̓��c�_�����ԁv �X���̉E��A����̘e�̃K�[�h���[����w�ɑo�̓��c�_������ŗ����Ă���B�E��ɂ͂i�q���ߕt���Ă����B  �u�ו���������v �E��ɍו���������A�O�ɑ傫�ȉ���^���N������B  �u�����ق̑O�̓��c�_�v �E��̕��Ì����ق̑O�ɑo�̓��c�_�A���̌�ɑ傫�ȐƉ���̔肪�����Ă��������̐����A�ǂ�Ȃ���ꂪ�L��̂��͕�����Ȃ������B���̓��c�_�ɂ��䒌�������Ă���B 

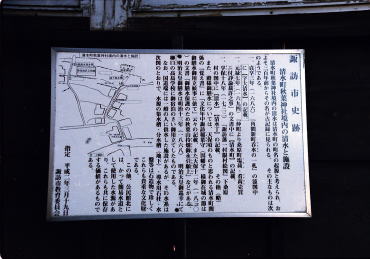 �u����ǂ̉Ɓv ���悢���z�K�̒��S���ɋߕt���Ă����B�E��R���ɐz�K���ˍ��Z�B�����̍���ɍ�������ǂ̓�K�Ƃ�����B�����̂��X�̂悤���B  �u�^���̑����v ���������_�͎l���H�ɂȂ��Ă���A�����͒��i�A�X���͎߉E�ɐi�ށB�����_�̍��ɐ^���̑����̋{�����������B�����̌����ɂ��i�q�̂���X�Y���I�h��������B������1662�N�̑n�ƁA�z�K��Ђ̐̕^���̋����炻�̖��O������Ă���B�X���ŗ��������o����B 

 �u�h�̒����݁v ���E�Ɋi�q����̒��������яh��̖��c��������B  �u�叼�@�v �E��ɏ�y�@�叼�@�A���͖{���̍H�����ő���ƃV�[�g�ŕ�܂�Ă���B�����ɂ͉ƍN�̘Z�j�������P�̕悪����B���P�͉z��55����̂��č��c�̏��ƂȂ邪�A�ƍN��G���Ƃ̕s������z���̐g�ƂȂ��z�K�̐z�K�����痊�i�ɗa����ꂽ�B  �u�������v ���ׂ̗ɗL��̂����@�@�閭�R�������B  �u�{���v ����ɂ͓h�ĕǂƂȂ܂��ǂ̐��{���A�ׂɂ́w���ʂ̂�{�����@������x�ƕǂɑ傫�������ꂽ�傫�Ȍ����B���X�͍��������ɂ���B������1756�N�̑n�ƂʼnƑ��o�c���Ƃ��B���̕ӂ��z�K�̎��ǂ���A�𑠂��W�����Ă���B 
 �u��l�v �������E�܂���z�K�w�̕����ɐi�ށB�����E��ɂ���̂���l�A�ؑ��̌����̈ꕔ�ɎO�K������Ă���B������1789�N�̑n�ƁB  �u���P�v �ׂ��d���ȑ����̓X�Ƒ��������P�B�����͖���28�N�ɖ��X�E�ݖ��̏��������番�Ƃ��Ď��n�߂��Ƃ����B 
 �u�≮�ꂪ�L�����Ƃ����钓�ԏ�v �E��ɂ���z�K�������ԏ�̕ӂ肪�≮��̂������Ƃ����鏊�B  �u��z�K�����H���W�v �≮�ꂪ�L�������Ƃ��������̂����Ȃlj����������A���ԏ�̃t�F���X�ۂɁw��z�K�����H���W�x�����t�����B���W�͂����Ă����̒��S�ɂ���̂ł��ꂪ�؋��̈�ƌ�����B 

![�����Ղ����z�K�w���ʂ�]��](ksk22-15.jpg) �u�����Ք�v ���̌����_�̉E��������s�̊p�Ɂw�j�Ւ����Ձx�̔肪�����Ă���B���̓��͔ˎ��ˎm�����p�����ƌ����B�E�ɐ܂ꂽ���������Ŗ��`�ɂȂ��Ă���z�K�ȈՍٔ����̂Ƃ���ō��ɐ܂��B  �u�g�c�̃}�c�v ������o�X�̕ЉH�̃o�X��A�E��f�p�[�g�̒��ԏ�̈�p�A�u���b�N�̊R�̏�Ɍ����ȏ�������B���ꂪ�z�K�s�V�R�L�O���́u�g�c�̃}�c�v�B �͂邩�������ɉ��������A����ɂ��ƃN���}�c�ŁA�����270�`300�N�A�����ˎm�g�c�����F�q�傪���\3�N�i1690�j���狝��8�N�i1723�j�ˎ咉�Ղ̑������ɐ��s�����Ƃ������A�������́B�g�c�ƒ뉀�ɗL�������̂����a�̂͂��߂ɍb�B�X�������ɈڐA�����B 
 �u�ꗢ�ːՁv ����̉ƂƉƂƂ̊Ԃɏ������܂��āw�ꗢ�ːՁx�̔肪����B���ɂ́w�b�B�����\�ˁx�̉��������B������������茩�߂����āA�����Ԑ�ł��������ƋC�t�������Ԃ��Ă����B 
 �u���ʐΐ_�Ёv ���̕ӂ肩��͎R���̂�⍂��ɂȂ����Ƃ�����ɉ����ĕ����`�ɂȂ�AJR�͍����𑖂��Ă���B�E��A�X�����班�����܂������Ɂw���ʐΐ_�Ёx�̔�ƁA��铔�A�̒����������ăX�M�̖ؗ�������B  �u��̋{�_�Ёv ���炭�s���ĊX�������E��ɐΊ_�̂���̂��w��̋{�_�Ёx�B�������Ă��܂������������̐_�Ђ̓����̍a�ɊW�������B����ɂ͈��ꂪ�L���āA�́A�i�F�̗ǂ����̒n�ɏZ��ł����Ր_�̍����P�����A�z�K���_���炱�̒n���~�����Ƃ���ꂽ�̂����ۂ������߁A��������o���Ȃ��悤�ɂƐ_�Ђ̑O�̐�ɋ����˂��邱�Ƃ��ւ���ꂽ�ƌ����B 
 �u�S�ʌ��X�����z�K��������v ���̕ӂ�ɗ��Ă���Ɛz�K�������o�����B�͑S�ʌ��X���Ă���悤���B�Җ]�̌�_�n��͌����邩�ȁH  �u�Ȃ܂��ǂ̑��Ɖ����ɉG�Ђ��̂���Ɓv ���̏W���ɂȂ��č���ɂȂ܂��ǂ̑��Ɖ����ɉG�Ђ��̂���ƕ���ł���B�����̏���̓X�Y���I�h���ƌ������́A���{���ʼnG�Ђ��ƌĂ�ł���^�C�v�ł���B�G�ɂȂ镗�i�Ƃ��炭���Ƃ�Ă���B 

 �u�i�q�˂��������v �i�q���肪���ɑf���炵���B�ێ��Ǘ��͑�ς��낤���A����ł���B�����܂ł��c���ė~�����Ɗ�킸�ɂ͋����Ȃ��B  �u�o�̓��c�_�v �X���̍��薯�Ƃ̒��ԏ�ɑ傫�ȑo�̓��c�_�A���ǂ��O�Ŏ��g��ł���B  �u�Γ�����v �E����R�������Ă��āA�X�����։����o���i�D�ɂȂ����Ƃ��낪�w�Γ�����x�ƌĂ�鏊�ŁA�R�A�X���AJR�A�����A�Ίݒʂ肪�������ɏW�܂��Ă���B�ڂ̉��ɂ͐z�K�Δ����فB���O�̒ʂ肱������𓊂�����ɓ͂������B�����炵���ǂ��w�����V�c�������x�Ɓw�������Γ���x�̔肪�����Ă���B�������猩���z�K�Ɍ�_�n�肪�����Ă���B�����B 



 �u�z�K��Љ��ЏH�{�v �ڂ̑O���ς��ƊJ���A���ɂ͒��ԏ�A�E�ɂ͑傫�ȁw�z�K��Ёx�̐Β��Ɖ��ɒ���������_�悪�L����B���R���������܂߉��x�������Ƃ���B�Ƃ��Ƃ����z�K�ɗ����̂��B  �u�傫�Ȓ��A��̐_�y�a�v �悸�͂��Q�肪��ƒ�����������B���ɃJ�[�u���Ȃ���ɂ₩�ȍ�����Ɛ^���ʂɑ傫�Ȓ��A�ꂪ�|�������_�y�a������B���̗�������䒌��������B���N�͐\�N�Ō䒌�Ղ̔N�i�ЂƐ\�̔N�A6�N�Ɉ�x�̊J�Áj�B���̂����鏊�Ŋό��|�X�^�[�����|�����B 
 �u�V�ߖ{�X�̐悪���R���E�]�˕��ʁv �Q�q���ς܂����̊X���ɖ߂�Ƃ����͖�O���A�M�B�����⊢���݂̂��X�����ԁB���̐�E��ɉ��r㻂ŗL���ȐV�ߖ{�X�B����Y�̊��V���g�����f�p�ȉ�������i�A����6�N�̑n�ƁA���̌����͖����̎u�m��l�V�����l�̉��~�������Ƃ��B�����L�O�̂��y�Y��5�{�w�����ăU�b�N�ɋl�߂�B���̒����H�����R���ƍb�B�����̍����_�Ő悪�]�˕��ʁA���������ʂł���B ![�V�ߖ{�X�̐悪���R���E�]�˕���](ksk23-07.jpg) �u���R���Ƃ̍����_�Ȃ̓��v ���R���Ƃ̍����_�A�����H�̉E��ɒ��ԏꂪ���肻�̉��̕ǂɂ͖ؑ]�H�����}��̉��z�K�h�̏�i���������[�t�ŕ`����Ă���B�ǂ̑O�ɂ͊���̔�Ȃǂ�����B�������≮��≺�z�K�O���̈�Ȃ̓����L�������B������w�b�B�������R�������V�n�x��A�w�Ȃ̓��x��A�w���ʁx�̃��j�������g�A�w�Ȃ̓��x�̉���A�w���R�����z�K�h�≮��Ձx��ŁA�≮��Ք�ɂ͍b�B�����I�_�E�]�˂\�O���\�꒚�Ƃ���A����̃E�H�[�N�̂܂��ɏI�_�̈�ł���A�����ė���������������Ă���B������ɍ��]�˂��\�ܗ������A���ʋ��s�֎��\�����O���Ƃ���A���R���o�R�̍]�˂܂łƋ��s�܂ł̋�����������Ă���B���̉���������������ƂɂȂ�B 

�y�[�W���ǁ@����23�N4��30�� �@�ʐ^�lj��@����23�N7��29�� |